内容説明
日本中世芸能の世界を、「勧進」「天皇」「連歌」「禅」という四つの切り口から論じる。経済活動の原動力としての勧進が芸能を包含していく過程、天皇制のなかの祓穢思想と芸能との発生のかかわり、位相の変化の連なりを集団の連関のなかで生み出す連歌のダイナミズムと美学、禅が孕むバサラ的思想。超域的な視点から能楽研究を拓いてきた第一人者の眼で歴史資料から鮮やかに見出される日本中世文化の全容を描く画期的講義の記録。(講談社学術文庫)
目次
まえがき
一 勧進による展開
二 天皇制と芸能
三 連歌的想像力
四 禅の契機──バサラと侘び──
本書で扱う主な文献
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しずかな午後
6
能・猿楽を中心とする中世の芸能を、勧進・天皇・連歌・禅という切り口から見ていく。よく言えばスケールが大きいのだが、悪く言えば主観的な印象論も多くて読んでいて白けた。網野・黒田俊雄・高取正男とかの論を無批判に取り入れているのも怖い。ただ、個々のテキストの読みは面白く、そして説明がうまい。『正徹物語』『筑波問答』『遊楽習道風見』など、これまで読んでいなかった作品の魅力が知れたのは良かった。また、『伊勢』123段をもとに俊成・定家・家隆と和歌の情景が変化していくのは興味深かった。2023/07/22
六点
5
「祓い」と「連歌」、そして「禅」をキーワードに中世日本の「芸能」について重要な視座を提供してくれる。清水克行氏や呉座勇一氏の本と続けて読むと「ムロマチ・メソッド」の物凄い暴力的な面白さが理解できる。2018/05/24
小物堂社
2
民間が公の場をつくっていくという矛盾。現代に通ずるものがあるのか、どのようなことでも「今」に結びつける能力が人間にはあるのか。どっちにしても勉強になる。勧進と禅はまた他の本でも読んでみたいと思った。中世の本は難しそうな本が多いけど、読めそうなものがあれば積極的に読んでみよう。2017/05/23
はちめ
2
「勧進」「天皇」「連歌」「禅」どの章も刺激的で面白い。たとえば禅の動的な側面の指摘とバサラの関連などはもっと追究されても良いのではないか。好著良著。2017/01/26
矢切複眼斎
2
勧進のところで「公ではなく民間活力で文化を支えるのがいいこと」的なことが書いてあったけど、そういう大義名分のもと文化活動費が削られたハシモト的な政策を見た後だと無邪気にそんなこと言ってられまへんなあ2015/05/31
-

- 電子書籍
- ウチの皇太子が危険です【タテヨミ】第2…
-
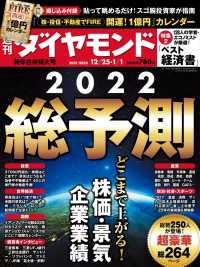
- 電子書籍
- 週刊ダイヤモンド 21年12月25日・…
-
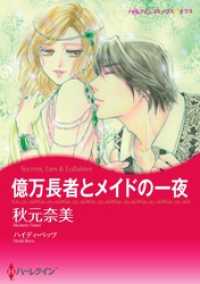
- 電子書籍
- 億万長者とメイドの一夜【分冊】 3巻 …
-
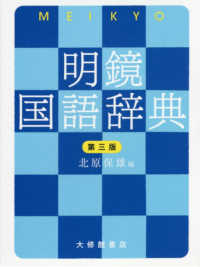
- 和書
- 明鏡国語辞典 (第三版)
-
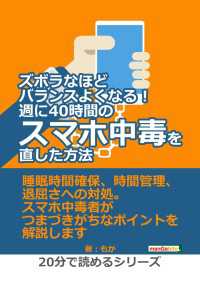
- 電子書籍
- ズボラなほどバランスよくなる!週に40…




