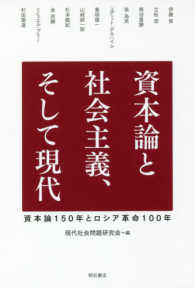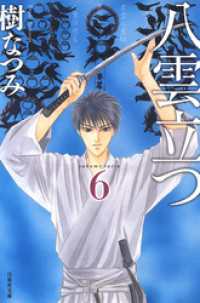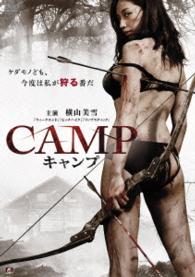- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「ウェブ」と「アメリカ」を考えるための新たな基本書の誕生。批評の新次元を開く待望の書。著者の池田純一氏は、デジタル・メディアの黎明期からの専門家であり、コロンビア大大学院で公共政策・経営学を学びました。ニュースや事象をいちはやく分析、ウェブと社会の関わりを洞察するブログ「FERMAT」(http://www.defermat.com/)は、高い評価を集めています。●Apple、Google、Twitter、Facebookは、なぜアメリカで生まれたのか? ●Googleを支える思想とは何か? それはこれからどこに向かうのか? ●FacebookとTwitterの本質的な違いはどこにあるのか? ●ウェブの展開は「ソーシャル」という概念を、どう再定義していくのか? ●ウェブによる国際化(全球化)に、ビジネスマンをはじめとして人々はどう対処していったらよいのか? これらの問いに答えながら、本書は同時に、「ウェブはアメリカの文化的伝統を、いかに継承・具現しているのか。社会の変容にどう寄り添い、国境を越え、結果として世界を動かしていくのか?」という壮大な問いに、歴史、社会、経済、思想、工学、建築、デザインなどの分野の境を超え、端正でやわらかな文章で語っていきます。ウェブが抱いてきた夢=「構想力」の源流をたどり、ゆくえを探る、斬新かつ根源的論考です。(講談社現代新書)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
18
けっこう難解な本だった。けれどカウンターカルチャーとウェブの関係性という切り口の考察は初めて読んだのでとても新鮮だった。文化的背景もさまざまな影響を及ぼしている可能性があるわけで(それがウェブのような最先端のものであっても、いや、だからこそ)それを考慮に入れて考えなければいけないのだな、と知った。2014/03/01
sabosashi
11
インターネットやウエッブが知の仕組みを換えるということは、もう長い間いわれてきた。つまりは世界の構造を換えうるということでもある。わたしたちはそう期待してきたものの、実のところはどこまで換わってきたのか、戸惑わざるをえないのも事実。 インターネットなどの歴史や役割に触れたものは数多くある。水面下での動きと、可視的な動きとを見極めるのは困難さがともなう。わたしたち素人のみでなく、専門家でさえ、曖昧なことしかいえないのも事実。 2018/10/23
森
11
フェイスブックやツイッター、グーグル関係に少々興味があり、図書館で借りました、なかなか濃厚な内容半分以上は理解しきれません、私の分野ではないのですが、フラー、ノイマン、ウィトゲンシュタイン、レヴィストロースなど記載がみられ親近感を感じる。分野が違うと、同じ言葉でもまったく使い方が違うようである、例えば「ポストモダン」、建築史的には、近代の後の意匠、装飾再評価だが、〜中略〜、なかなか良い本でした。また再読します。f^_^;)2016/08/18
踊る猫
9
アメリカのカウンターカルチャーや 19 世紀の文化/政治まで概観し、様々な思想家の著作を軽やかに縦横無尽に言及しながら Google や Facebook や Twitter などのネットが生み出した文化を分析した書物。一章毎に一冊本が書けるのではないかと思うくらい手強い話題を新書らしくスマートに纏めており、若干詰め込み過ぎな感もある。だが若い読者、つまり既にネットに触れた時に Google があったという方には新種のアメリカ論として参考になる部分が多々あるのではないか。冷笑的ではない良心が好ましく思える2017/06/02
読書実践家
9
全球時代の構想力というのが気宇壮大な気がした。ウェブが生み出した空間の密着感は我々に、新興国とのつながりも提供する。単に環境が悪くて見出されない人材との接点をモバイルインターネットは与えてくれる。みんなの知恵を合わせることができるだろうか。そして、これから紙媒体の本の価値はどこへ行くのだろう。よほどの技術革新が起きて、本にとって変わるツールが出てこない限り、読書に勝る知的な手段は少なくても私にとっては見つからない。2016/03/13