内容説明
1973年夏、東京拘置所。『カール・マルクス』『ウルトラマン』等、夢見る囚人達と所長『ハンプティ・D』の間で演じられる可笑しくも悲痛な思想劇。『さようなら、ギャングたち』『ジョン・レノン対火星人』と並び著者の原点を示す秀作。
目次
第一話 虹の彼方に
第二話 ラストダンスは私に
第三話 クリストファー・コロンブスのアメリカ大陸発見
第四話 戻っておいで『カール・マルクス』
第五話 戻っておいで『カール・マルクス』結末篇
著者から読者へ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
優希
89
夢や虚構に彩られた世界が広がっていました。この曖昧さが著者の好みの空気感なのでしょう。どこかおかしくて哀しみを湛えた雰囲気が心地よい。サイケデリックさも文学として昇華してしまう力というものを持っているような気がする短編集でした。2017/05/06
佐島楓
59
「さようなら、ギャングたち」「ジョン・レノン対火星人」と同じ文脈で読まないと理解ができない。実を言うと、読んでいても何のこっちゃとなった。3部作の中で、一番著者に寄り添わなければいけない作品なのではないか。「さようなら~」が名作なのは私の中で揺るがない。2018/10/20
おさむ
37
タカハシさんのデビュー後最初の作品だそうですが、エキセントリック過ぎて読むに耐えませんでした。タカハシさんの初期作品群は生理的にダメですね。残念。2016/02/19
踊る猫
33
正確さ・明確さを求めて連ねられた言葉が、滑稽にもその言葉自体の端的なくどさによっていつしかそうした当初の意図から遠ざかることは往々にしてある。今回の読みで、この作品において高橋はそうした言葉の持つ矛盾した魔力に挑んでいる印象を受ける。ふだんスムーズに伝わっている言葉がいったいどういうマジックを孕むのか、その真髄まで言語表現を脱臼させて冗語とも受け取れる表現やジャーゴンやスラングを豊富に盛り込むことで、私見ではウィトゲンシュタインの哲学やあるいは実験的なヒップホップ、コンセプチュアル・アート的な境地を見せる2024/09/15
田氏
22
「全世界を書こうとしていた」という小説。60年代~80年代前半のできごとや固有名詞がならび、それらは意味を剥ぎ取られて裸で踊っている。その踊りが何のかたちに見えるか?横浜や東京拘置所の場所の記憶、まずそのように見える。次に見えてくるのは、言葉そのものであった。そして言葉に弄ばれ、無限後退や停滞や循環や非到達性の、さびしい場所へと押し込まれていく『カール・マルクス』たち。『虹の彼方に』は、そして『虹の彼方に』の彼方、そのまた彼方は、脱出口となったろうか。あるいは消失点。前回よりも何まわりも楽しく読めた再読。2023/09/10
-

- 電子書籍
- エボニー【タテヨミ】第92話 picc…
-
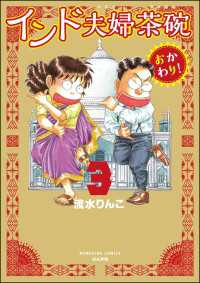
- 電子書籍
- インド夫婦茶碗 おかわり! (3) 本…
-
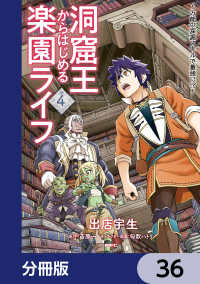
- 電子書籍
- 洞窟王からはじめる楽園ライフ ~万能の…
-
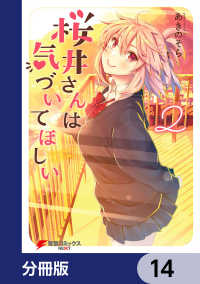
- 電子書籍
- 桜井さんは気づいてほしい【分冊版】 1…
-

- 電子書籍
- 愛しすぎた報い【分冊】 7巻 ハーレク…




