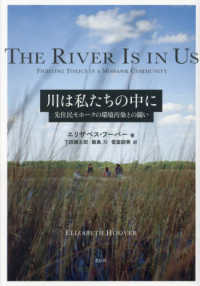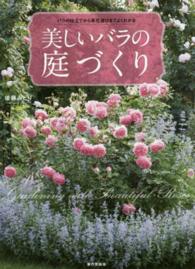内容説明
新しきが「花」である
室町時代、芸能の厳しい競争社会を生き抜いて能を大成した世阿弥の言葉は、戦略的人生論や創造的精神に満ちている。「秘すれば花」「初心忘るべからず」など代表的金言を読み解きながら、試練に打ち勝ち、自己を更新しつづける奥義を学ぶ。テキスト時にはない新規図版、ブックス特別章なども収載。
[内容]
はじめに マーケットを生き抜く戦略論
第1章 珍しきが花
第2章 初心忘るべからず
第3章 離見の見
第4章 秘すれば花
能と世阿弥 関連年表
ブックス特別章 能を見に行く
あとがき──テレビの後で
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ちゃちゃ
112
室町時代、能は世阿弥によって大成された。名著『風姿花伝』は、彼が父観阿弥から受け継いだ能の奥義を子孫に伝えるために著した能楽論。本書は、不安定な時代に芸術という市場をどう勝ち抜いていくべきかを記した戦略論という斬新な視点を持って、作品を分かりやすく読み解いた能の入門書でもある。人口に膾炙する数々の馴染みある言葉、「初心忘るべからず」「秘すれば花」等を、芸術論的な視点のみならず人生論・戦略論として位置づけ、現代を生きる私たちに有用な言葉として解説する。常に現状に安住せず創造を続ける姿勢こそが「花」と知る。2020/02/11
buchipanda3
96
「よこまち余話」で引用された世阿弥の言葉にもっと触れたくてこちらを。いずれ本編の現代語訳を読んでみたいが、まずは能楽や世阿弥の世界の入口として。「風姿花伝」は世阿弥が残した能楽論の書。だが本作の冒頭ではドラッカーのイノベーション理論との共通点が語られる。その現代性から一気に身近さを感じた。芸術論に留まらず人生論へと繋がる。「よこまち余話」で惹かれた理由もそこにある。「老いてのちの初心」による規範からの自由、「目前心後」による柔軟性など改めて自身を振り返ることに。そして己を知り、却来の意を掴みたいと思った。2025/01/02
アキ
67
世阿弥の風姿花伝が現在まで残る理由のいくつかがわかる。鎌倉時代に起きた日本語の変化により約600年前の文章が現代に生きる我々でも理解できるようになった。これは親鸞や日蓮といった新しい宗教家により、わかりやすい物語や宗教の言葉が現れたことによる。またマーケットを意識した戦略が述べられていること。能の興行主が寺や神社から義満のような将軍や貴族に変わったことで流行が生まれたから。現代でも通じる「珍しきが花」「初心忘るべからず」「離見の見」「秘すれば花」などはこの書から来ている。能を見に地元の能楽堂に行ってみたい2019/11/29
ころこ
47
このあと『風姿花伝』を読むわけだが、その前に読んでみた著者の文章が素晴らしい。我々は『風姿花伝』を能の演技方法や見方を教えてくれる本だと思っているが、もっと射程が広く、能により文化や人生にも通じる物事の新しい切り口や活用方法を創造したことだと指摘している。著者もまた『風姿花伝』を読むことで、能の伝統芸能としてのイメージに新しい見方を創造しようとしている。能はオリジナルの創作劇ではなく、文学や和歌に典拠を持っているので、現代の映像化のように、原作を視覚化するための装置であり、形式はそのための仕掛けだという。2022/11/09
Book & Travel
34
外国人が日本文化を紹介した本で、有名な書として世阿弥の「風姿花伝」の話が出ているのを目にしたので、エッセンスを知りたくて、原典を読もうとして挫折し、本書を手に取った。芸能論、技術論という印象を持っていたが、それだけでなく、「初心」「時節感当」「離見の見」「秘すれば花」など、人生論、子育て論、仕事論としても読め、勉強になった。能自体は退屈なイメージがあったが、本書に見方の解説などもあり、何より著者の能への愛が伝わってきて、600年以上も続いている伝統芸能だけに、一度は見てみたいと思うようになった。2016/02/14
-

- 電子書籍
- ちはやふる plus きみがため 分冊…
-

- 和書
- はじめまして!ましろくん