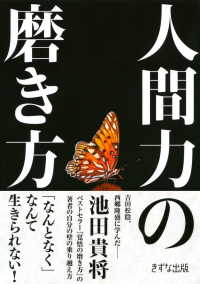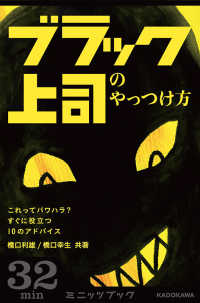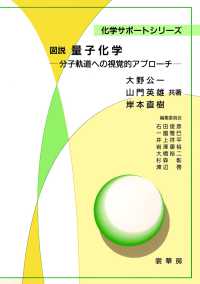内容説明
紀州、そこは、神武東征以来、敗れた者らが棲むもう一つの国家で、鬼らが跋扈する鬼州、霊気の満ちる気州だ。そこに生きる人々が生の言葉で語る、”切って血の出る物語”。隠国・紀州の光と影を描く。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みっちゃんondrums
30
「差別」を知らないで屈託なく生きるほうがよいのか、「差別」を知った上で意識するほうがよいのか、はたまた「差別」を知った上で知らない振りをするのがよいか……もう知ってしまったけれど。する側もされる側も、何故そんなに拘るのか。中上氏の小説は読み物として面白いと思ったし、このルポも傍観者として興味深く読んだ。それでよいのか、問うてばかりの感想になってしまうな。2018/06/21
Shoji
29
著者が実際に紀伊半島に点在する被差別部落を歩き、取材し、有形無形の差別の形を著したルポである。民俗学で言うハケとケの「ケ」に焦点をあてて叙述されており、民俗学の教科書のようでもあった。2024/07/04
こうすけ
24
中上健次が故郷の紀伊半島をめぐり、部落差別を真っ向から取材したルポルタージュ。差別とはなにか?という大テーマを掲げて、集落の人たちを訪ね歩く。といっても、そこは小説家によるルポ。紀は記であり、木、気、鬼であるのだ、という視点のもと、差別と物語の切り離せない関係性を解き明かす。際どいテーマの連載ものだったため、ある集落の人たちから「事実と違う」と呼び出しを食らい、糾弾された中上。しかし「言葉を持つわたしは、書き言葉を持たぬ者の批判にさらされる義務がある」と、甘んじて矢面に立つ。この覚悟がかっこいい。2022/09/23
しゅん
19
小説より読みやすい。地理や状況が呑み込めないところ多いものの、抒情性がすんなり入ってくる。『枯木灘』は作者と「紀州」が同化している感じがして入り込む隙がない、という印象を持つのだけど、こちらは中上と紀州のズレが主題になっていると思う。書き言葉を持つことが、インテリの定義(=紀州の地から乖離する人)である、という感覚が息づいている。部落のリアリティが私にはないのだなと思ったし、それはつまり天皇制にピンとこないということと同義かもしれない。2024/05/27
ナハチガル
17
初・中上健次。熊野古道について知りたかったのだが、紀行文というよりどっぷり同和問題についての本だった。著者自身が被差別部落出身であることもあって、今までそこにあることをうっすらと気づいていながら正視してこなかったものを目の前で濃密に展開されてしまった感があるが、息苦しくはなく風通しはいい。そのあたりの動物的なカンというか、研ぎ澄まされた感覚が全編を支配している。荒々しくも繊細。小説を読むのが楽しみだ。「美しさというものに、差別という回路を通すことによって、性と宗教と暴力が増幅されて出てくる」A。2025/10/18