内容説明
考えに考え抜き、自分の底を突き破った先にあるものは――。世の不条理、生きる悲しみ、人生のさだめなどを、歩きながら沈思黙考し、「日本人の哲学」を誕生させた西田幾多郎。自分であって自分でなくする「無私」とはどんな思想なのか。その根源にある「無」とは何か。純粋経験、理性と精神、死と生、論理と生命、根本実在……難解な言葉をかみくだき、「西田哲学」の沃野を、稀代の思想家が柔らかな筆致で読み解く至高の論考。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
245
中々面白い分析だった。西田幾多郎って取っ付きにくい哲学のイメージだが、実際は日本的な哲学だったんだなと知った。1回西田幾多郎の原作にもあたってみたいが難しそうだな。2015/09/08
1.3manen
41
デンケン先生(9頁)。東京と違い、京都は最先端、目先の問題から距離を置くことが特質(24頁)。日本語で自己表現し他人と議論、会話できるようにすることがコクサイカよりも先決(31頁)。西田先生の信念は、哲学が人生から始まり、人生へ向かい、人生で終わる。生きるための哲学(37頁)。西洋文化は有の文化で、日本文化は無の文化。西田先生も西洋の有の論理と東洋の無の論理を対比(84頁)。逆対応とは、相対的なものが自らを否定することで絶対が現れる。絶対と相対はそれぞれ自己否定することで、他方へと現れること(137頁)。2015/01/29
テトラ
32
西田幾多郎の哲学は悲哀から始まったのだという。悲哀、それは生きる上で誰の身の上にも訪れて避けられないもの。どうして私は悲しむのだろう。悲しむ「私」とは何なのか。それを突き詰め、自己を覗き込んだ時その底にあるという無。現代社会の様々な事象や時事的な事柄に触れながら著者の思考は展開する。哲学を学ぶ上で必ずしも哲学者の人生を知る必要はないとは思うけれど、西田幾多郎に関してはその哲学が自らの生の経験に根ざしたものであったことからも知っておいて損はないと思う。2016/02/25
calaf
17
西洋的な「神」を仮定した考え方、つまり全ての物事をその世界の外から見るという考え方。これは、少なくとも自分、つまり私に対しては使えない。私は必ず世界の中にいるものだから。逆に、世界の中にいる私は、私を消し去る、つまり無の境地に至って初めて無から生じる。絶対的な神という存在は存在しないので、時間の流れを外から眺めることも出来ない。つまり歴史というものも存在しない。。。まとめかたあってる?ともかく、面白い考え方。でも難しい・・・2015/03/05
masabi
15
正直本書を読んでも理解できる箇所が少なかった。筆者は他の著作でニヒリズムの処方箋が西田幾多郎と京都学派にあると書いていたので、西田幾多郎の思想の他にも期待していたのだが、それについての言及はなかった。思うに、合理主義など西欧近代の産物がニヒリズムに繋がったのなら、西田の近代とは異なる論理を以てニヒリズムを打破しようとしたのではないだろうか。西田の思想は、主体を無や場と考え近代の主客分離とは異なった日本の思想である。2015/09/06
-
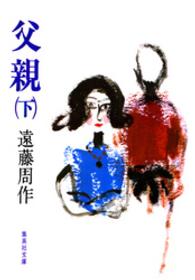
- 電子書籍
- 父親 〈下〉 集英社文庫
-
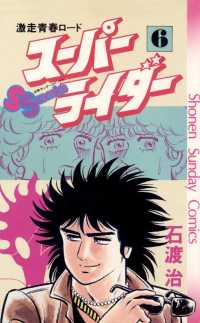
- 電子書籍
- スーパーライダー(6) 少年サンデーコ…




