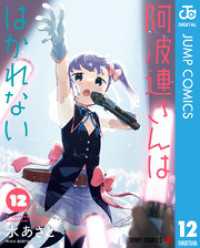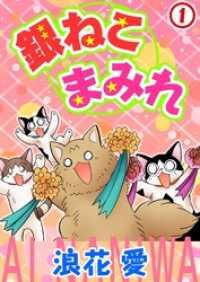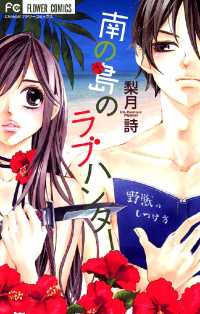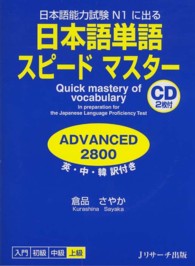内容説明
戦後日本の中心には,常に「働くこと」があり,それがみなを豊かにすると信じられていた.しかし,そのしくみは,他ならぬ日本的「働かせ方」のグローバル化によって,破壊された.どこで道を誤ったのか.迷走する日本の労使関係の来歴をたどり,新たなしくみづくりに何が必要かを考える.
目次
目 次
はじめに
第一話 「働くこと」の意味
1 なぜ働くのか──社会の中心にあった「労働」
2 生きていくために必要なもの
第二話 日本的労使関係システムの成立
1 力のせめぎ合いが社会をつくる──労使関係
2 「成功」とその代償──日本の経済成長
第三話 転機──日本企業の海外進出
1 世界にキャッチアップした一九八〇年代
2 日本に追いつけ
第四話 日本の「働かせ方」が壊したもの
1 国境を越えた労使関係システムのパラドックス
2 浮かび上がる矛盾
第五話 「働くこと」のゆくえ──生活を支えるしくみづくりへ
1 交渉力を取りもどす
2 労働と生活をつなぐ──コミュニティ・オーガナイジングに学ぶ
3 日本でなにができるのか
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
29
たとえば「同一労働同一賃金」と聞くときのモヤモヤ。当然だ!という思いとともに、そもそも違う人同士の労働が同一ということなんてない、とも確信するからだ。この本はそのモヤモヤを、これまでの日本とアメリカの労使関係史コミで晴らしてくれる。◇良かれと思って取り組んできた努力は、今の働きにくさ・働かせにくさを生んでしまった(エラそうにしながらも、使う側も苦しみながら、だ)。この難題に著者が提示するのは、「コミュニティ・オーガナイジング」という処方箋。そう、まずはみんな、答えは見つからないということを前提にしなきゃ。2015/02/17
ゆう。
22
社会の中心であった労働は、もともと労使の関係のなかで築かれてきたものだと著者は指摘します。しかし、こんにちの労働市場改革は、非正規雇用などを大量に生み出し、労使の関係を崩していると述べて、「働くこと」の意味が崩されてきていると指摘します。読んでいて、労働組合のあり方が、たいへん重要なのだと思いました。労働組合は、労使関係にだけ目を向けているわけではなく、社会問題そのものも自分たちの取り組みべき問題として活動していたからです。こんにちの労使関係のあり方、労働組合のあり方、働く意味を考えることができました。2015/04/19
ちいちゃん
10
とてもわかりやすかった。産業革命以降の労使関係の歴史を紐解きながら現在の厳しい労働環境の解決策を論じている。一人一人がなぜ働くのか、そしてどのように生きるのかを考える必要があり、その手助けをするのが直接参加型の民主主義システムだという。2016/05/07
どら猫さとっち
6
私たちは、何のために働いているのか。本来働くということは何なのか。それをもう少し深く考えたい人には、本書はうってつけだろう。本書には日本の働き方の過去から、これからの対策法までが満載。それにしても、日本の働き方を壊したのは、国際化が進み、グローバル化が高まったとき、競争社会が加速したことにあるといえる。ブラック企業も、そうした流れから生まれたものだろう。この国は人間らしい働き方について、もっと考えなければならない。2014/12/04
hiroshi0083
5
現在の私たちを取り巻く労働環境の改善。その提案が本書の目的である。 そこへの道のりとして、本書はアメリカと日本の労働環境の歴史を紐解いていく。 両国の歴史を振り返る中で、1980年代の日本の働き方が、アメリカに、さらには世界に影響を与えた事実が明らかになる。その影響が巡り巡って、現在の日本の労働者を苦しめているのだ。 世界に影響を与えた日本の働き方。それは、1950年代にエドワーズ・デミングが伝えた統計的品質管理手法だ。(コメントに続く)2017/04/29