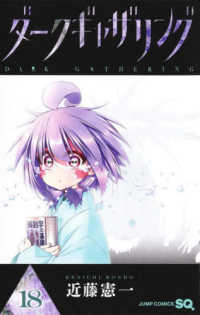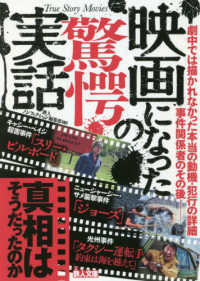内容説明
1986年から2011年まで、26年間にわたって行なわれた精神科病院での講演録。現場の臨床の真っ只中で常によりよい治療に向けての工夫を重ねてきた著者の、新しい技法発想の萌芽と展開が一望でき、多数の著書の解説としても読める。「誤診と誤治療」をはじめ、「精神療法におけるセントラルドグマの効用」「問題点の指摘の仕方」「臨床力を育てる方策」「フラッシュバックの治療」「双方向性の視点」「治療者の偏見」など、どの講義内容も示唆と警鐘と破格におもしろいアイディアに満ちている。
目次
サポートについて
精神療法におけるセントラルドグマの効用
問題点の指摘の仕方
痴呆老人の看護
私たちの精神健康法
粘り強い心をつくる
対話精神療法の初心者のために
共感について
知ること、知らせること
SSRIが登場してからの連想〔ほか〕
-
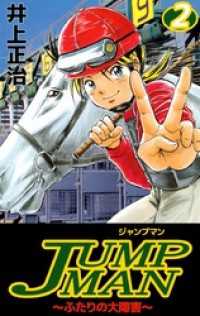
- 電子書籍
- JUMPMAN ~ふたりの大障害~(2…
-
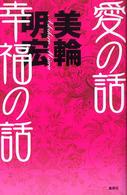
- 和書
- 愛の話幸福の話