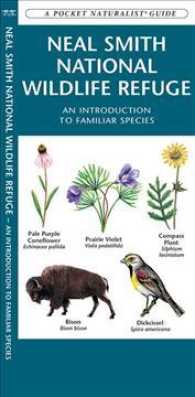- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
言葉と文化、自然と人間の営みに深い思索を重ねてきた著者が、世界の危機を見据えて語る《日本人の使命》とは? 外国人が日本語を学ぶとなぜか礼儀正しくなる「タタミゼ効果」の不思議や、漢字に秘められた意外な力、そして日本の共生的自然観を西欧文明と対比させつつ、繊細だが強靱なこの国の感性を文明論として考える。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tamami
50
2014年刊。つい先ほど再読完了。初読時の付箋がそのまま残り、一旦目を通したのは確かであるが、幾つもの記憶漏れを発見する。ただ今回再読する中で、現在自分が言葉と文化というものに対して抱いている考え方のかなりな部分が、鈴木先生の言説の中に認められることに気がついた。自分なりに、独創的と思っている様なことでも、案外元は割れているということか。太古以来自然と共にある日本文化のあり方を、改めて教えられる。そのユニークなあり方こそ、日本語・日本文化がこれからの世界に貢献できる点ではないかという先生の主張に全く同感。2021/12/31
1.3manen
43
相変わらずの独創的鈴木節。私は人間だけがこの世界で特別の、他の生物一切から隔絶した特権的な地位を占める存在ではないと確信しています(9頁)。水琴窟:廃水を利用する究極の省エネ型の、音を楽しむ装置が江戸時代に開発(79頁)。重要なことは、とにかく詩作活動と呼べるものに、多くの日本国民が、今でも何らかの形で自発的に自分の時間を割いているというころ、それ自体が驚くべきこと(81頁)。2017/02/12
しんこい
11
まだ新たな著作が読めるとは思いませんでした、日本こそが世界を変えられるという論も、この著者の言うことなら信じたくなりますが、それよりも文化が環境に合わせる緩衝地帯となり生物としての人間は変わらず世界中にひろがっているとか、動植物の多様性が失われるのと、言語の多様性が失われるのと原因は同じ根っことか、そんな発想を楽しむだけにしたい。2015/01/07
Nobu A
10
鈴木孝夫先生著書6冊目。筆者著書をそれなりに読んでいないと独創的で多少面食らうかも。相変わらずの鈴木節炸裂。自然破壊に歯止めが掛からないグローバリゼーションの対抗策に日本語を含めた日本文化を広めることを提唱。恐らく誰にでも経験がある「タタミゼ効果」を援用し、自然征服の西洋文明でなく自然調和の東洋文明を日本から発信する必要性。該博故にか、話が時折四方八方に飛ぶが、パプア族や菌塚の例等、とても興味深い。ただ、盆栽や家畜も人為的で矛盾を感じる。「大学とは本来(学問でなく)人間とは何ぞやを探求する場」が心に響く。2020/07/09
くま
7
タイトルとは関係なく なぜ日本が戦争を始めたのか? アジア諸国は全員日本を恨んでいるのか?など、日本の戦後教育における歴史教育のあり方に疑問をもつようになった。 日本人としてのトラウマはこの歴史教育から生まれている気がする。だから、日本を愛し、自信をもって国際社会に発信できない日本人が多いのかもしれない。 世界で唯一被爆国で、広島に住んでいるからこそもう少し明治維新以降について、日本史を勉強しなおしたくなった。2017/05/31
-

- 電子書籍
- パンピア伝記【タテヨミ】第43話 pi…
-

- 電子書籍
- 剣道日本 2022年2月号