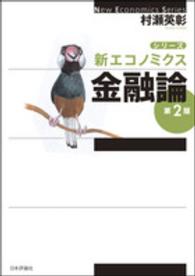内容説明
1776年に発売されるや、たちまち希代の名著としての地位を確立したギボンの『ローマ帝国衰亡史』。「国家の衰亡、文明の衰退は必然なのか」という人類永遠のテーマを考えるうえで、この書の存在を欠かすことはできない。本書ではこの歴史的名著を抄訳し、時代ごとの解説を付している。2000年に単行本として発刊以来、毎年刷りを重ね支持を得た、この翻訳書をルビを増やし解説も加筆修正して、装いも新たに新書<普及版>として刊行。下巻(第VIII章~終章)では、ユリアヌス帝の登場からローマの滅亡までの歴史を眺望する。人間の歴史を淡々と、しかしながら卓越した文章力で描ききる本書は、愛・悲しみ・歓喜・不安・嫉妬・憎悪・恨み・苛立ち……といった人間の感情・情動から、歴史がつくられていくことを伝えることに成功している。そして人間の行動の背後にある「歴史の法則」を読み取るのは、読者諸氏に委ねられている。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
バズリクソンズ
24
下巻で遂に西、東の両ローマ帝国の滅亡が著されるが、盛者必衰という言葉をこれでもかと思い知らされる内容。数多の建築、美術品もローマ帝国が起源であり、キリスト教を国教に制定し、元老院議員が権力を樹立し、貿易の点でも他の地域を圧倒していた様子が伺えるが、ギボンの原書より大分端折られている為、細かな内容まで把握するには不十分ではある著書。これをベースにまたローマ史関連の書籍に挑戦したい。この下巻は東ローマの凋落振りをギボンがそれまでの筆致を異にして書かれていて、この部分が大変興味深く読めた。巻末の年表も素晴らしい2022/12/17
イプシロン
20
全11巻におよぶ衰亡史を上下巻にしているので、不満足はある。が、大約のローマ史を知りたいなら十分な内容だろう。衰亡の要因をマクロで考えるなら、社会情勢の変化に対して情報・人・物・金が追いついていけない巨大な領土をもってしまったからと読んだ。むろん、人のもつ貪欲さ、虚栄心なども見逃せないのだが。下巻最大の読みどろこは11章にある「人類の進歩について」だろう。人類がギボンのあげた3項目への叡智を失わない限り、なんとか生き残っていけると思えたからだ。2018/05/12
MAT-TUN
9
上下巻ともに満足のいくものだった。イスラム教やイスラム社会に対するギボンの考察も興味深く、偏見無く本質を考察している。ヨーロッパで消滅しかかった古代ギリシアの知的遺産をアラビア語に翻訳し、その命脈を保っていたことなども明記している。これは立派な態度だと思う。衰亡の過程をつぶさにみると、私は清国のアヘン戦争前の世相と少しダブって見えた。清国では尚武の精神に富む屈強な満州騎馬隊の栄光が、建国より数百年ののち消え去り、堕落して使い物にならない軍が残っていた。そんなときでのイギリスとの交戦に勝利の可能性は無かった2013/07/06
matsuri_n
1
西洋史素人、なんとかこの大著(抄訳だけど)を読み終えることができた...古代、紀元前から始まって読み終えたら中世に至る壮大さよ。そういう意味では、千年紀を超えて1つのシステムが存続することにそもそもの無理があるのかもしれない。とはいえ、(内戦したり分裂したり)ローマ帝国という同一性がどこまであるかは正直なところ疑問では? 解説にもある通り、ある意味でローマは今でも生き続けていると言えるか。2023/12/17
かみかみ
0
評価:★★★★☆ ユリアヌスからテオドシウス死後の東西分裂、そしてオスマン帝国によるコンスタンティノープル陥落まで。植民地時代の英国において、「ローマ人としてのアイデンティティ」がローマとその周辺の民衆の傲慢さや排他主義を生んでゴート人によるローマ陥落を招いたこと、イスラーム諸王朝が古代ギリシャ以来の学芸を保護、深化させたことを指摘する、という客観的記述に徹したギボンの姿勢は評価したい。2013/09/12