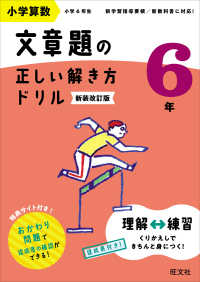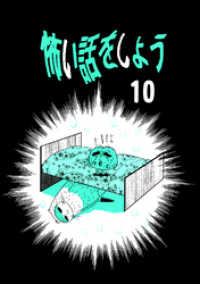内容説明
読解教育では、学習者の理解を補助するために、教材となる文章に興味深い内容を盛り込んだり、分かりやすい内容にしたりするなど、様々な工夫がなされています。しかし、文章の理解には、文章それ自体の言葉の特性以上に、人間の記憶のシステムや情報処理のメカニズム、視覚や聴覚などのあり方、読み手の特性などが大きく関わっています。そのため、効果的な読解指導を行うには、このような人間の理解の仕組みを知ることが有用であるといえます。本書は、このような、文章を読み、理解する行為の仕組みを具体的かつ実証的に裏付けられたデータに基づき解説しています。日本語教育や国語教育の現場で読解教育に携わる方々におすすめの一冊です。※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、予めご了承ください。試し読みファイルにより、ご購入前にお手持ちの端末での表示をご確認ください。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はら
11
丸二日間かけて読了。大変勉強になった一冊です。研究データを示しながら、解説してくれているので、分かりやすかったです。面白い研究にすっかり引き込まれました。ただし、認知の話がほとんどで、読解教育についてはちょこっと触れただけなので、期待している内容と少しギャップがありました。2014/06/08
YIN
2
読解ストラテジーに関してはだいぶ前からいろんな論文を読んでたが、ちゃんとまとまった本は初めて見つけた。この手の認知心理学系の本は助けになる。2022/05/25
satochan
2
外国人がどうやって文章題を解くのかに興味があったので読んでみた。人によって読み方は変わるかもしれないが、やはり、知識として知っているというのは大事なことだと思う。次の展開を予想し修正する能力なども必要だと思えた。読んでいて一番大事だと思ったのは、重要度の話だった。筆者が言いたいことと、読者にとっての重要度は一致するわけではない。いわれてみれば当たり前なのだが、学校が求めるのは、筆者にとって何が言いたいかのほうだ。テストではそれを抑えながら読むということを教える必要があるかもしれない。理解するって奥が深い。2018/10/01
まーれ
2
著者の講演会を聴いてとても興味深かったので、著作も読んでみました。文章理解は語の理解・文の理解より高次な処理であることがよくわかりました。2016/11/11
Nobu A
2
もうすぐ開講の新学期に行う連続講演会の最初にお呼びする講演者の著書を流し読みで再読。改めて読むと、前回とは少し違う理解構築が読解の興味深さと実感。それに、読解の認知過程の知見から読解教育への応用の難しさを改めて理解。ある程度語学習得が進んだら、時間的な制限や教材開発の苦労を考えると、多読が一番いいのかなと思ったりもする。勿論、解説や学習者のレベルに合った内容理解確認が必要だが。2016/08/30


![Tarzan(ターザン) 2025年7月10日号 No.905 [脳は、90歳まで進化する!]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-2151833.jpg)