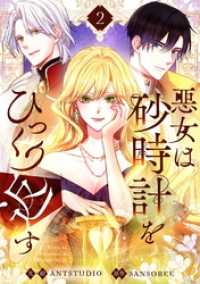内容説明
その文明観・自然観が近年再び見直されている寺田寅彦。科学と文学を高い次元で融合させた寺田に間近に接してきた教え子・中谷宇吉郎による追想録。自身も随筆家として名を成した中谷の筆致は、大正から昭和初期の「学問の場」の闊達な空気と、濃密な師弟関係を細やかに描き出す。漱石の思い出や、晩年に注力した「墨流しの研究」の紹介など、その話題は広範囲にわたる。(講談社学術文庫)
目次
第一部
寺田寅彦の追想
文化史上の寺田寅彦
指導者としての寅彦先生
実験室の思い出
札幌に於ける寺田先生
第二部
寅彦夏話
一 海坊主と人魂/ 二 線香花火と金米糖/ 三 墨流し
冬彦夜話 漱石先生に関することども
寒月の『首縊りの力学』その他
『光線の圧力』の話
線香花火
霜柱と白粉の話
球皮事件
先生を囲る話
一 その頃の応接間/ 二 フランス語の話/ 三 コロキウム/ 四 ディノソウルスの卵/ 五 田丸先生とローマ字/ 六 電車の中の読書/ 七 初めて伺った時/ 八 随筆の弁/ 九 パブロワの踊り/ 一〇 物理学序説/ 一一 人類学の一つの問題/ 一二 名人/ 一三 影画の名人/ 一四 本多先生と一緒に実験された頃/ 一五 ガリレーの地動説/ 一六 筆禍の心配/ 一七 水産時代の思い出/ 一八 雲の美/ 一九 全人格の活動/ 二〇 実験の心得/ 二一 ボーアの理論/ 二二 本/ 二三 露西亜語/ 二四 ある探偵事件/ 二五 赤い蛇腹の写真器/ 二六 ヴァイオリンの思い出/ 二七 日本の商人/ 二八 落第/ 二九 中学時代の先生達/ 三〇 冬彦の語源/ 三一 油絵の話/ 三二 学士院会員/ 三三 Rationalistの論/ 三四 恐縮された話/ 三五 昼寄席/ 三六 津浪と金庫の話/ 三七 俳句的論文/ 三八 理研の額/ 三九 セロの勉強/ 四〇 僕が死んだら
第三部
墨流しの物理的研究
墨流し/墨の粒子の大きさ/水面に拡がった墨膜の厚さ/水面に出来る墨の膜の固形化/圧縮による墨膜の固化/木片の端で作った墨膜の孔/墨膜に出来る細胞渦
墨並びに硯の物理学的研究
墨を磨る装置/使用した墨と硯との種類/墨のおり方の測定/墨と硯との間の摩擦係数の測定/墨粒子の直径の測定/磨墨による硯面の変化/各種の硯の比較/磨墨による摩擦係数の変化/墨のおり方と粒子の直径との関係/墨のおり方と摩擦係数との関係/水中の電解質の影響/以上の実験結果の吟味
『物理学序説』の後書
後 書
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
shinano
オザマチ
オザマチ
オザマチ
ねね