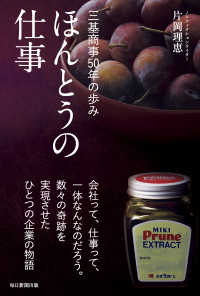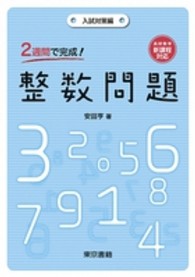内容説明
藤原氏一族が権勢を誇る平安時代。内供奉(ないぐぶ)に任じられた僧侶隆範(りゅうはん)は、才気溢れた年若き仏師定朝(じょうちょう)の修繕した仏に深く感動し、その後見人となる。道長をはじめとする貴族のみならず、一般庶民も定朝の仏像を心の拠り所としていた。しかし、定朝は煩悶していた。貧困、疫病に苦しむ人々の前で、己の作った仏像にどんな意味があるのか、と。やがて二人は権謀術数の渦中に飲み込まれ……。(第32回新田次郎文学賞受賞作)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あさひ@WAKABA NO MIDORI TO...
112
本屋が選ぶ時代小説大賞2012、第32回(2013年)新田次郎文学賞のダブル受賞もなるほどとうなずける。平安時代後期の仏師定朝の生涯。仏教や仏像に関心がなければ積極的に手にとってみたいとは思わないかもしれない。御仏は貧困に身をやつし死に瀕している人々を救うことができただろうか。どんなに評価され美しい仏像を造ろうとも、それにいかほどの意味があるのか。世の中の矛盾や貧困に憤り、苦悶しながらも生きる意味、造仏の意味を模索していく定朝。登場人物のキャラクター、物語の構成ともに群を抜く。いい作品に巡り会えた。2019/08/02
たま
72
最近平等院を拝観する機会があり、建築や仏像の優美さに今更ながら感心してこの本を読んだ。澤田さんの平安物は今年になってから3冊目、既読の2冊はともに道長の繁栄の影になった人々の悲哀に焦点があったが、この本でも仏師定朝が、不遇の敦明親王や道隆系の人々との交流を通して己の彫るべき仏の姿を追求する。敦明親王には全く同情できなかったが、彼を気遣う彰子付き女房や彼女のために自らを犠牲とする僧侶など様々の人々が定朝の道を照らす灯りとなり、平等院の阿弥陀仏に結実する過程は読みごたえがあった。(単行本で読んだが文庫で登録)2024/06/24
のぶ
70
仏閣を訪れる際に定朝の名を耳にすることが多く、澤田さんが定朝の生涯を描いている事を知り読んでみた。時代は平安。若くして仏師としての才能を開花させ、多くの仏像を作っていた。意外だったのは、僧侶の隆範との交流はあるものの、本人は仏教への信心はあまりなく、だが美しい仏像を彫りたい一心で活動していたように描かれていた事。当時の時代背景も良く表現されており、とても興味惹かれる小説だった。クライマックスは終章の平等院の阿弥陀如来の作成。その時代に連れていかれたような臨場感があった。2017/10/28
がらくたどん
69
再読♪大河ドラマでは道隆が関白になり息子伊周は若くして大出世で中関白家は絶好調のタイミング。だが残念、舞台は道長独走で道隆の家系は風前の灯で平安京も災害病苦の暗黒街。上り詰めると心配なのは子孫と来世。出家だ寺だ仏像だ。道長も人の子。僧侶を恃み仏師を集め。並ぶ役者は伊周の鬼子「荒三位」道雅・道隆の妻貴子の異母兄弟設定隆範・悩める天才仏師定朝。不遇な三条帝の嫡子敦明と因縁の花山帝の息女で道長の娘彰子に仕える中務が絡む。道長政権の火薬庫で何も起きない訳がない。怨嗟に荒ぶる心の隅で人はなお一条の慈悲を待っている。2024/04/08
NAO
60
若いころから天賦の才を持っていた仏師定朝。だが、彼は、貧しい孤児たちと接するうちに、自分が仏像を彫っても、それで貧しい者たちが救われるわけではないことに苦悩する。貧しい者には貧しい者の、富めるものには富める者の苦しみがある。末法の世にあって、僧や仏師は人々の苦しみとどう関わっていったらいいのか。道長の時代は王朝文学盛んな時代で、様々な作品が残っているとはいっても、こういった側面からとらえた作品はあまりなく、主流から外れた人々の悲哀など、とてもよく描けているのではないかと思った。また、平等院に行たくなった。2018/03/20
-

- 電子書籍
- 辛口バーテンダーの別の顔はワイルド御曹…
-
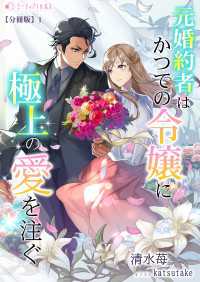
- 電子書籍
- 元婚約者はかつての令嬢に極上の愛を注ぐ…