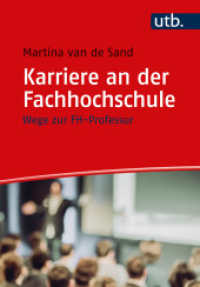内容説明
五木寛之が日本史の深層に潜むテーマを探訪するシリーズ「隠された日本」の第3弾。現在、大阪城が建てられている場所には、かつて蓮如が建立した石山本願寺があった。大阪の底に流れる信仰心の側面を探る第一部。また、国際色豊かなエネルギーを取り込み、時々の権力者としたたかに付き合ってきた京都に前衛都市の姿を見る第二弾。現代にも息づく西の都の歴史に触れる。
目次
第1部 見えざる日本人の宗教心(大阪は宗教都市である 寺内町という信仰の共和国 現代に息づく「同朋意識」と信仰心)
第2部 日本のなかの“異国”を歩く(京都は前衛都市である 磨きぬかれた「市民意識」 伝統と革新のせめぎあいの中で)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
50
大阪を宗教の観点から、京都を新進の観点というちょっと変わった視点から描いており普段言われている事とのギャップが興味深い。大阪は太閤以前の石山本願寺の影響を中心に、宗教が大阪弁や文化、文学に与えた影響を説いている。東京の官に対して大阪の民、その中心にあるのが、寺内町を中心とした真宗の影響というのは興味深い考察。無論それだけではないだろうけど、要因の一つではあるのかなあ。対して京都は如何に京都が新進の気風に富んでいたかということを論証。こちらも豊富な実例と共に、一風変わった京都文化論として極めて興味深かった。2014/06/23
1.3manen
29
寺内町:寺の敷地の内部に抱きこまれた町。周囲が土塁や水濠で囲まれている(38頁)。信長は非常に好奇心が強い人だった(44頁)。大きな問題は、大坂が寺内町から城下町に変わったということだ(46頁)。寺内町は一種のアジール:権力は及ばず、DVの妻の駆け込み寺(55頁)。蓮如は、社会から蔑視されていた人びとに、職業的なプライドを持たせた人だった(58頁)。素晴らしいものをつくるということは、人間にとって喜びであり生きがいである。2015/12/06
slider129
27
偉い先生が書く新資料に基づく本も良いが、五木さんの様に文化や宗教に造詣が深い作家が書いた物は肩肘張らずに楽しめる。秀吉の大坂城の前に顕如が築いた石山本願寺を取り上げているが、信長が支配地で行った楽市楽座は実は顕如が石山本願寺の寺内町で始めた自治特権を真似たものだと言うことは初めて知りました。そんな大坂は商業都市である前に真宗の影響を多分に受けた宗教都市だったと言う説はとても興味深い。また、古都京都は保守的なイメージが強かったのが、元々は先進的で時の権力者を手玉に取るほど柔軟的な前衛都市だとする考えも新鮮。2017/12/17
ラウリスタ~
11
タイトルから期待していたものとは違っていた。奈良や長野の宗教都市や、日本のどこかの「前衛都市」について書かれたものではなく、宗教都市「大阪」と、前衛都市「京都」についての本。大阪は商売の町である以前に宗教都市である!というなかなか目から鱗の話、いわれてみればそのとおり。大阪の商魂をヴェーバーの「プロテスタンティズムと資本主義」に引きつけるのはなかなか面白い。京都は普通、そりゃあ京都は昔っから新しいもの好きだからね。2014/08/04
くらひで
10
寺内町の歴史を持ち、宗教都市としての性格を帯びた大阪。一方、保守的で伝統を重んじると思われている京都は、実は常に新しさを追求し前衛的な性格を醸し出している、というエッセイ。一般人とは視点を少しずらした著者らしい持論を展開し、興味深いものがある。確かに両都市とも市民意識(シティズン)が高く、自分たちが自分たちの街を作っているんだという誇り高さを感じられる。都市としての機能を有し、文化的に発展してきた都市の本質が隠されているように思われる。2016/08/01
-
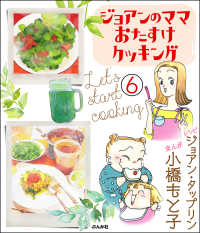
- 電子書籍
- ジョアンのママおたすけクッキング(分冊…
-
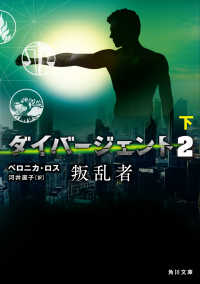
- 電子書籍
- ダイバージェント2 叛乱者 下 角川文庫