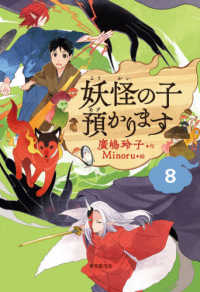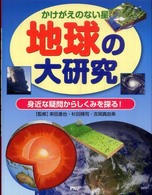内容説明
【第36回サントリー学芸賞 芸術・文学部門 受賞作】 ギリシアから近現代にいたる「言語起源論」の流れを追えば、それはそのままヨーロッパの思想展開史に重なる。把握不能な「言語生成の瞬間」を、それでも見ようとした無数の試みは、近代に至って何を見出したのか。気鋭の著者による渾身の西洋思想史。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kaizen@名古屋de朝活読書会
95
言語が自然か、人為か。パンタグリュエルは、「自然的に言語をもっているというのは間違いだ。」自然説に対して、慣習説もある。 「バベルの塔」を例に言語展開についての記述も。 ソシュール、メルヴィル、チョムスキーが話題に。 他言語の機械翻訳を設計する際に、起源言語のような中間言語を考えるより、実用的で複数の言語体系の要素を含んでいる英語に変換した方が効率的だという経験則あり。コンパイラの変換の際にも、どのような中間言語がよいか、特定の言語(C言語、LISP等)を用いるかの選択の際にも、起源言語との比較をする事有2014/09/09
内島菫
29
そもそもが言語起源論は星の数ほどもあるそうなので、その系譜を本書の分量をもってしてもコンパクトにまとめたと言えるのだろうが、やはり少し煩雑で読みにくかった。けれども、自分なりに要所を押さえていけばかなり示唆的な本。まず言語の起源を問う行為自体に矛盾がある。三次元にいる人間が四次元内での思考を持てないように、言語の中にいる我々は、言語の起源が呼び寄せる言語の外を手に入れることはできない。2017/11/21
loanmeadime
16
暑い最中に読む本ではなかった、というのが正直なところです。ソシュールによれば存在しない「言語起源」について、無数の空論を生み出してきた主題を扱った論説をプラトンからチョムスキーまでたどります。人類の進化を習っている現代の我が身には、オランウータンと人間の間に断絶を認めないモンボド卿の考えが最もしっくり来ました。言語を扱うことは認識を扱うことなので、当然、哲学的な下地が求められるのですが、高校の倫社の時間は教師の似顔絵かきに勤しんでいた私には、その辺が大変でした。2021/08/07
Koning
15
冒頭のコンピュータによるコーパスの比較でプロトほげほげ言語を探す研究が紹介されてたんで、最終的にはノストラティックあたりのアレな学説までを紹介する物だと思っておりました。というより古典的哲学屋っぽい(実際どちらかというと言語学者というより哲学屋列伝になってたり)人間の言語の起源は如何に?という問いを2500年位に亘ってご紹介という本 だった。最終的にチョムスキーとか出てはくるけれど、個人的にはこの手のアプローチをやってどうすんだね?というトコがあったりする訳で(汗。うーん(汗2014/07/24
isao_key
12
驚くべき情報量。プラトンからチョムスキーに至るまでの言語起源論についての変遷を追っている。凡例に英語、フランス語、ドイツ語で書かれた文献からの引用はすべて原点から訳出したとあるが、これだけの冊数を原典で読みこなすとは、ただ事ではない。40代前半にして言語学の大家がなすような仕事を完成させてしまった。日本人が書いたとは思えないような論の進め方で、西洋の思想家、学者たちの学説を紹介する。読みにくい本ではないが、水準が高く、一筋縄ではいかない読み応えのある本。全編を通して、カスパー・ハウザーを中心に据えている。2016/01/17
-
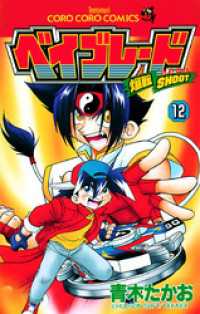
- 電子書籍
- 爆転シュート ベイブレード(12) て…
-
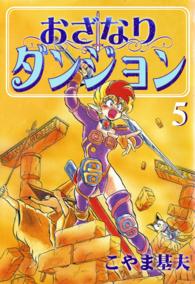
- 電子書籍
- おざなりダンジョン 5巻