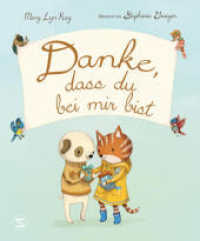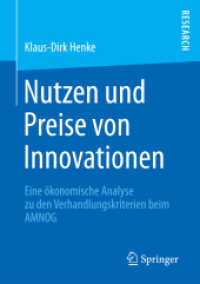- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
主な舞台は東京の下町。
そのあたりでは伝統的な露店商を「テキヤさん」と呼んでいる。
「親分子分関係」や「なわばり」など、独特の慣行を持つ彼ら・彼女らはどのように生き、生計を立て、商売を営んでいるのか―。
「陽のあたる場所からちょっと引っ込んでいるような社会的ポジション」を保ってきた人たちの、仕事と伝承を考察。
目次
第1章 露店商いの地域性(静岡あたりの見えない壁 「文化の壁」と「なわばり」 ほか)
第2章 近世の露店商(名称の歴史的変遷 近世の香具師はどのような人びとだったのか ほか)
第3章 近代化と露店―明治から第二次世界大戦まで(近世の江戸と近代の東京の間に 近代的知識人と露店商い ほか)
第4章 第二次世界大戦後の混乱と露店商―敗戦後の混乱期(闇市の出現 誰が闇市の主導権を握るのか ほか)
第5章 露店商いをめぐる世相解説―一九六〇年代以降(親分子分関係 なわばり ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鉄之助
293
最近話題の「反社会的」集団、に興味があって読み始めた。祭りにはつきものの、屋台店を出す「テキヤ」は「7割商人、3割ヤクザ」と、テキヤさんたちが自ら言っているという。ちょっと危なそうだが、祭りの賑わいには不可欠、な気もする。全国の祭りの中にはテキヤ排除をうたう所もあるが、なかなか一概には、色分けできないようだ。その意味で「7割商人、3割ヤクザ」の表現がとても面白かった。ヤクザは極道だが、テキヤは神農道に従う。神農は、古代中国の農業や薬の神的存在。その違いが興味深かった。2023/06/24
マエダ
67
まずテキヤとは実際何なのかである。ルーツや現状、文化を知れたことは良かった。2019/02/24
AICHAN
64
図書館本。露店商(テキヤ)はヤクザなのだと、この本を読むまではそう感じていた。昔、倶知安の秋祭りに出向いたとき、祭りの後に居酒屋に寄った。そこには露店商とその家族たちが大勢いた。物騒で近寄れなかった。そういう露店商もいるようだが、大半は神農という神を崇める特殊な集団らしい。江戸時代の香具師(ヤシ)がそのルーツだという。全国にはたくさんの露店商集団があり、それぞれ縄張りを持っているが、例えば素人の露店商でもその縄張りに入れるというように、縄張り意識は薄い。縁日等で見られる露店商の多くは地元の集団である。2019/10/18
エドワード
35
幼い頃、今よりはるかに露店が多かったように感じる。今でも露店商は謎の存在だ。「誰に断って店出してるんだ」というマンガのようなセリフは本当だった!親分子分もなわばりも、実際にあるんだねェ。だがそれは日本の社会に普遍的に存在する、という指摘に納得、想像以上に社会学の本だった。「7割商人、3割ヤクザ」という言葉が的確で、うさんくさいけれど、祝祭空間に欠かせない人々。電気を配線し、掃除をして帰る人々。そこには秩序がある。茶髪のお兄さんがスマホで遊んでいるのを見ると、やっぱり普通の人だなと思う。飴細工が懐かしいネ。2019/07/16
ホークス
35
テキヤの来歴とその世界を分かりやすく教えてくれる。女性である著者が、実際にアルバイトに入って長期のフィールドワークを行い、親分たちにも度々取材している。大変だったと思うが、おかげで取って付けた様な理屈がなくて面白い。最近は世の中が個人情報に厳しくなり、この様な研究が難しいらしい。人間は本来グレーな生き物なのに、中途半端に潔癖かつ怠惰になってしまい、建前だけで生きられると思っているのではないか。本書は生身の人間の切ない姿を見せてくれる民俗学本である。2016/09/15
-

- 電子書籍
- カリスマ失墜 ゴーン帝国の20年