内容説明
あらゆる世俗的な思想を根こそぎにして、「善く生きる」賢者の生を追求した、西洋近代哲学の父……それこそが、デカルトである。死者や病者によりそって思考し、哲学者の神とは何かを語り、まっすぐな倫理をめざす。そこにこそ、「我思う故に我在り」の哲学者の、いまなお読み直すに足る魅力がある。教科書的な知識としてではなく、現代を生きるわれわれ人間のための至高の哲学として、デカルト哲学を描き出した不朽の力作。(講談社学術文庫)
目次
序章 思想を捨てる
第1章 離脱道徳―精神的生活と世俗的生活
第2章 懐疑―世俗的生活からの脱落
第3章 死にゆく者の独我論
第4章 哲学者の神
第5章 最高善と共通善―宗教の可能性
第6章 賢者の現存―善く生きること
終章 魂の不死、私の死
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
白義
18
デカルトの「我」を死にゆく者がそれでも絞り出す我として、一見全ての自由を奪われた囚人の、病人の最後にして唯一絶対の自由として称揚し、他のいかなる自由や善よりもその自らの精神を享受すること自体が究極の自由にして善であると高らかに謳い上げた、デカルト哲学の倫理的可能性を限界まで切り開こうとする名著。デカルトの伝記的事実に、テクストに忠実に寄り添い書いているにも関わらず、本書がデカルトの客観的な解説書と思うものはまずいないだろう。恐らく本書は生前のデカルトの意志すら無視して自らの問いを彼とともに貫こうとしている2017/05/28
またの名
10
体力も時間も金も発言能力も活字を追う能力もないので公的討論のテーマをつかみ損ねるし、場にそぐわない的外れな話をしてしまう病者や貧者。哲学的問題としてどちらかを助けるしかないと仮定される複数の命。はっきり言ってデカルトを法外に逸脱した現代思想寄りの読解を衝き動かすのは、そんな風に誰もが排除と犠牲に加担し死者を喰らって生きている現実から目を背けたり殊更に向けさせたりする状況を許すすべての思想を根こそぎにする倫理。懐疑によって近代を創始した権威の象徴とも見えるデカルトが、あらゆる下劣をなぎ払う為の武器に変わる。2016/07/07
有沢翔治@文芸同人誌配布中
7
小泉さんの言いたいことは解る。だけどデカルトを持ち出さなくても言えるどころか、デカルトと全く関係なような。強引に引き寄せた感じが否めない。http://blog.livedoor.jp/shoji_arisawa/archives/50218922.html2017/04/29
セツコ
1
著者のデカルトへの熱量に時に少し慄きつつも読了。「人間の主要な部分は精神であって、人間は知恵の探究にこそ配慮しなければならない。そしてこの知恵が、精神の真実の食物であり…最高善である」知恵が精神の真実の食物…。これは現代社会で忘れられてしまっていることではないだろうか。「良く」生きようとするあまり、誰も知恵に見向きもしなくなっている気がする。精神に知恵を与え育てること、つまり、本を読んだり経験したりしながら考えることが楽しみを感じやすくさせ、結果として「善く」生きることへもつながるのではないかと思う。2022/10/21
まつゆう
1
「私」が動き、意識し、作用するというその力能そのものを存在の根拠として、全面的に肯定すること、喜ばしいと認めること、そして実際にそのような生き方をしている賢者がいることを認めること。デカルトの哲学をここまで自家薬籠のものにした本にはなかなかお目にかかれない。このような哲学、そしてそこから紡ぎだせる倫理で何ができるか。狡い市民的な倫理を「根こそぎ」否定することはできようが、そこが問題なのではない。更に賢者から学ばなければ。2014/07/08
-

- 電子書籍
- 勇者に敗北した魔王様は返り咲くために魔…
-
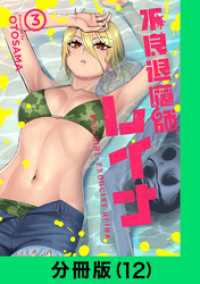
- 電子書籍
- 不良退魔師レイナ【分冊版(12)】 L…
-
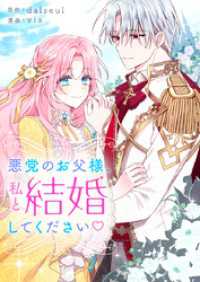
- 電子書籍
- 悪党のお父様、私と結婚してください 【…
-
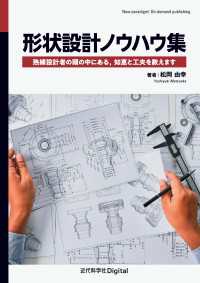
- 電子書籍
- 形状設計ノウハウ集 - 熟練設計者の頭…
-
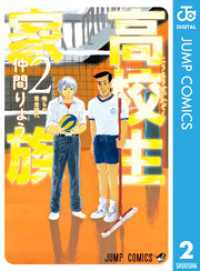
- 電子書籍
- 高校生家族 2 ジャンプコミックスDI…




