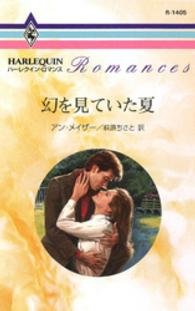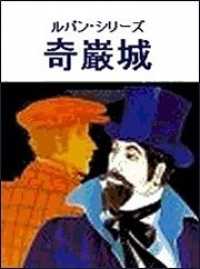- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「新しい社会秩序は可能だ(エンゲルス)」。青年マルクスは「賃金」「資本」「利潤」について根源的に考察し、古典派経済学と格闘しつつ独自の経済学を確立していった。本書は、彼の出発点と成熟期の二大基本文献と、理解に欠かせない「賃金」草稿と「代議員への指針」を付録にし、詳細な解説を加えて独自に編集した。『資本論』を読み解くための最良の入門書。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かわうそ
45
マルクスが言う労働とは単なる労働ではありません。自分のために物をつくってもその物を商品とは呼べないんですね。他人のために作り、自ら消費することのない、社会的労働によって形成されたものが商品でありその商品の価値を作るのが社会的労働です。この社会的労働が彼の言う労働に他ならない。そして、その労働が資本主義社会の価値を作り上げる。実はプロレタリアの労働は必要労働と不払労働に分解できる。この不払労働はブルジョアによって搾取されているというのがマルクスの主張であり、どんなに賃金が高くてもここの本質は変わらないです。2023/04/20
かわうそ
36
逆説的にマルクスは資本家になって労働者から剰余労働という形で搾取しろと言っているようにしか聞こえない。賃金とは生産論であるというのは次の意味である。分配論というのは完成したケーキ(お金)をいくつかに分けて配るという意味に過ぎないが、生産論は生産の段階で分け前が決まっている状態のことを指す。つまりは賃金は資本家の利益が上がったところで大して上がることはないということになる。資本と賃金というものを比較してみると常に相対的に賃金の率というのは低く抑えられるものである。 故にサラリーマンは搾取される存在でしかない2025/02/22
かわうそ
28
「通常の平均的な利潤は商品を実際の価値以上にではなく実際の価値通りに売ることによって得られるのである。」一般的な理解としては商品をその価格を釣り上げることによって利潤を得ていると思われるがそうではない。あくまでも、労働者が不払労働をすることによって剰余価値が生まれ、それが資本家の懐に入るのだ。さらに、その労働者の賃金も労働時間の総体の価値として現れると思われるがそうではなくて、労働時間の支払運動のみが反映されるのだ。さらには、生産力の増大は労働者の労働を過酷にする。2022/02/28
1.3manen
20
労働そのものの生産費とは、労働者を労働者として維持するのに、彼を労働者へと要請するのに必要とされる費用(傍点30頁)。社会的な生産諸関係は、生産の物質的諸手段、生産諸力が変化し発展するとともに変化し変容する。生産諸関係は、社会を構成し、一定の史的発展段階における社会を構成する(傍点34頁)。賃金が増大するのは労働に対する需要が増大するとき。生産資本が増大するとき(103頁)。非正規の単価を上げるにはどうするか? 2015/01/18
たんたん麺
13
賃労働にとって最も有利な条件は生産資本ができるだけ急速に増大することである。2014/05/24