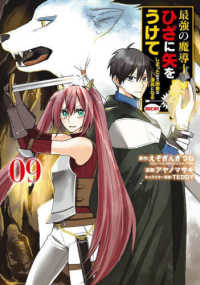- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
なぜ何かを好きになるのか? それはそのほとんどが無意識のプロセスで起きる。「好きになる」脳の原理を知れば、それを逆手にとって好きになってもえらえる。脳をうまく騙すことで“好きにさせる”錯覚の心理学。
目次
第1章 「すこし愛して、ながく愛して。」
第2章 見た目の情報で「好ましさ」が決まる
第3章 なんとなく好きにさせる王道テクニック―誤帰属・サブリミナル・ポジティブマインド
第4章 遺伝により決められた「好み」
第5章 すぐに使えるなんとなく好かれるテクニック
第6章 自分からちょっとは好きになる:勉強
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
マエダ
96
なんとなく好きに重点をおいているのが本書であり、人、物、勉強など人は何を嫌い、何を好きになるのかを心理学、脳科学的に解説している。2016/07/07
anco
10
「好きになること」と「欲しくなること」は脳内では別のプロセス。脳は視覚優位。好ましく思わせるには視覚と感情に訴える。好き嫌いは無意識に決まってしまう。自分の脳が処理しやすいものを好む。処理が流暢になることで誤帰属が起こり好ましく思うようになる。感情プライミング効果、良いものを見せて気分を向上させることにより、その後に見るものへの好感度へとつなげる。ポジティブマインドは好きと欲しいの架け橋。異性に好まれる表情、女性は笑顔、男性はプライドと恥を含んだ表情。好ましさは6秒で決まる、うなずく、笑顔を見せる、笑う。2016/01/28
futabakouji2
6
自分としては勉強の仕方がとても参考になった。記憶することは何度も解くのも大事だけど、時間を置いて覚える。そして復習は問題形式でやるといいようだ。あとは自制心の強さも大事。これはできそうなので取り入れてみる。2019/05/20
もも
3
著者の本は二冊目だが次々に書き出される心理学的実験の結果で飽きさせることはない。「少し好きにさせる」技術をメインに書かれた本ではあるが将来商店を開いてみようかなと頭の片隅にある私にとってはこの実験結果は多分に使えるのではないかと思う。そういった点で心理学と経済は深く結びついているのだなと確信する。昨今行動経済学がブームであるが頷ける。この本は私の心理学への探究心を確定的にしてくれた。心理学の面白さを実感。2017/12/03
yukari
3
なんとなく好きと感じる仕組みの解説。サブリミナル効果で、意識に昇っていなくても瞳孔が狭くなるなど実は体は反応しているという話や、ある物に対して脳での処理の流暢性があがると好ましく感じるという話が面白かった。この類いの本でよく出てくるのが、人は物語や理由付けが好きだという話で、そういう傾向があるというのを知るだけでも意思決定が変わる気がする。まあふつうに生きていたら「あ、これは脳の処理流暢性が上がったから好ましく思うのだ。誤帰属に注意!」とかは思わないよなあ。2016/06/05
-

- 和書
- 刑法総論 - 理論と実践