内容説明
薩摩、長州を中心とする反幕府勢力が、武力で倒幕を果たしたという「常識」は本当か。第二次長州戦争は、なぜ幕府の敗北に終わったのか。王政復古というクーデタ方式が採られた理由とは。強烈な攘夷意思をもつ孝明天皇、京都の朝廷を支配した一橋慶喜、会津藩の松平容保、桑名藩の松平定敬。敗者の側から、江戸幕府体制がいかに、そしてなぜ崩壊したかを描き出す。(講談社学術文庫)
目次
幕末政治史の常識について
幕末維新史研究の過去と現在
孝明天皇の登場
朝幕関係の悪化と孝明天皇の朝廷掌握
江戸幕府と孝明天皇の対立
井伊直弼暗殺後の政局と孝明天皇
一会桑の登場と孝明天皇
一会桑の朝廷掌握と孝明天皇
第二次長州戦争の強行と反発
一会桑による朝廷支配の崩壊
十五代将軍の誕生と大政奉還
王政復古クーデタ
鳥羽伏見戦争と倒幕の達成
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
saga
38
幕末を、薩長史観ではなく、孝明天皇、敗者である幕府の側からも考察した。学術的には、龍馬や西郷、高杉などの志士や新選組は枝葉末節なものらしい。外国に対する知見を持てなかった孝明天皇が、力を失いつつある幕府と相まって、自国と外国の力の差を実感できずに攘夷路線を突き進んだことが、結局は幕府の崩壊に繋がった。大政奉還後、薩長の武力討幕という野望を止める者は誰もいなかった。本当に日本国民を震撼させる王政復古クーデターが必要だったかは疑問だ。2020/02/06
樋口佳之
28
突然自らの決定を表明する徳川慶喜のドカン病/武力倒幕論ではない。いままで王政復古クーデタについて、イチかバチか武力倒幕をめざした冒険主義的な選択だったという評価があることは何度も触れた。しかし、西郷・大久保両者の書簡を素直に読むかぎり、これはどう考えても、戦いの相手に想定されているのは会津・桑名の両藩(なかでも会津藩)/江戸の薩摩藩邸を拠点に、江戸市中と関東各地で幕府を挑発するための行動を開始したことが大いに関係していたと、長年、一般的にはみなされてきた。しかし、いまでは、このような見方は否定2018/06/15
中年サラリーマン
17
幕末から明治が薩長ドーン!なイメージしかない僕には面白かった。一旦攘夷に大きく振れるのは、今の社会構造を望み外国がその構造を破壊するのではと恐れた孝明天皇の強固な意志というのが面白い。ゆえに政治権力を持って攘夷へ引っ張ろうとし一時はいいとこまで行くが井伊直弼に潰されかける。しかし、桜田門外の変で一変。そこに天皇の意を汲もうとする一橋慶喜、会津藩、桑名藩からなる一会桑体制とその崩壊過程。そして薩長ドーンや最後まで忠義をつくしたが貧乏くじを引いた感のある会津藩。幕末前夜を細かく振り返ることができて面白い。2014/04/12
MUNEKAZ
10
幕末の政治動向を「一会桑」政権から読み解く。孝明天皇からの信任をもとに京都の政局をリードした一橋慶喜・会津藩・桑名藩の勢力だが、その独善的な動きは薩長のみならず江戸の幕府や国元の家臣とも対立を生んだ点は面白い。慶喜の将軍就任は分裂していた幕府勢力を統一することになったが、同時にあくまで「一会桑」を主敵としてきた薩長側を「倒幕」へと追い込む要因となったのは皮肉である。慶喜も新政府も「どうしてこうなった」と思いながら、維新を迎えていたのではないかと思わせる一冊であった。2018/02/05
武夫原
8
明治維新では明治天皇が神格化され、その父親の孝明天皇が影が薄いですが、その理由も孝明天皇の考えにあったことが分かりました。孝明天皇や薩摩・長州を除く他の藩は倒幕を考えていなかったこと、薩摩・長州の藩内ですら倒幕を藩論として掲げることは困難であったこと、通説的な明治維新の筋書きが不確かなものであたことが説明されています。なかなかおもしろい本でした。タイトルに覚えがなかったんで買いました。ところが、文藝春秋から出ていた本の改題でした。同じ内容の本を知らずに読んでしまいました。2016/10/11
-

- 電子書籍
- Motor Magazine 2022…
-
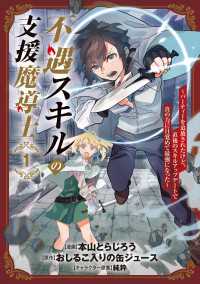
- 電子書籍
- 不遇スキルの支援魔導士 ~パーティーを…
-

- 電子書籍
- 奇跡のロマンス【分冊】 5巻 ハーレク…
-
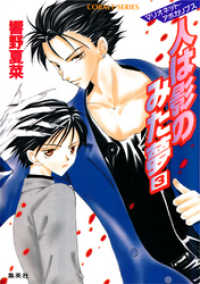
- 電子書籍
- マリオネット・アポカリプス 人は影のみ…
-
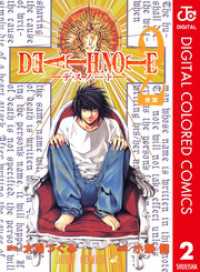
- 電子書籍
- DEATH NOTE カラー版 2 ジ…




