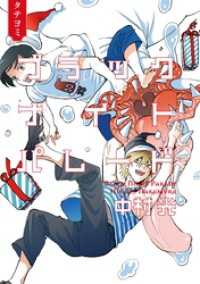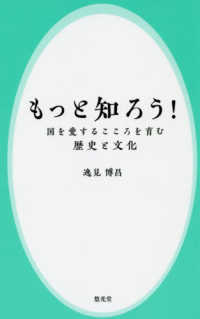- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
私たちは、いま手にしている書物の「物」としての素材や形態の変化について、どれだけ知っているだろうか。製本と装丁の本場、パリで学んだ著者が、本を成立させる各部の起源と変遷を辿る。西洋の書物史がすべてわかる、愛書家垂涎の一冊。
目次
第1章 書物の考古学
第2章 西洋の紙「羊皮紙」
第3章 本の誕生と製本術
第4章 ケルムスコット・プレス
第5章 モロッコ革を求めて
第6章 フランスの革装本
第7章 天金と小口装飾
第8章 花切れ
第9章 マーブル紙と見返し
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヨクト
21
本の始まり、そして革の本や模様、綴じ方等を取り上げた本。日本ではあまり見かける機会の少ない革の本にかなり憧れますが、はてさていったいその中身は本にする?と問われたら迷いすぎて夜も眠れねぇや。物としての本、電子書籍ではカバーできない本の一面がここにはある。2014/05/16
鳩羽
18
本の歴史を紐解くとき、ロゼッタストーンやパピルスといった物体の特性を無視しては語れない。それぞれの短所が改良されて、今の紙の本の形になったのがよく分かる。けれど、本の歴史というよりは細かい装丁の本といった感じで、花切れや小口だけで一章を割いているのがすごい。手間暇かけて装丁を施された本という存在は、中身にも価値があると信じられていたことの証でもあるだろう。そういう価値の見方を取り戻してみるのも、いいかもしれない。2016/04/26
Koning
17
物としての、工芸品としての、書籍の解説。クレイタブレットやパピルスから歴史を語るとこもあるけれど、やはり中世以降の洋書の構造的な解説というか、製本のあれこれ。流石にフランス装を自前で革装丁とかお金がなくて無理なんだけど、昔は親戚にも岩波文庫なんかですらこれと思った本はきっちり製本しちゃう人がいたもんです。骨董市なんかに来る業者なんかでもこの辺の知識の欠如してる人たちばかりなので(そもそも本をバラすしね、連中)そういう意味ではこうした文化が更にごく一部の金持ちの道楽になっちゃうんだろなとも。2014/03/14
ふろんた2.0
16
西洋の装丁技術やら、モロッコ革についてちょっとだけ賢くなりました。2016/03/07
itokake
14
本そのものについて、知らない世界を見せてもらった。ロゼッタストーンから始まる歴史が興味深い。先日、『羊皮紙の世界』を読んでいたので、さらに理解が深まった。モロッコ革で装丁された本が美しいというが、どこで見る機会があるんだろう。17世紀に突如現れた謎の製本家、ル・ガスコン。彼の装丁は抜群に美しい。おじさんの横顔が模様に紛れ込んでいる。芸術家としての署名なんだろう。その遊び心がいい。フランスでは少し前まで文学書を中心として多くの本が仮綴じで売られていた。購入した人が自分の好む書物に仕上げる。なんか素敵。2024/04/24