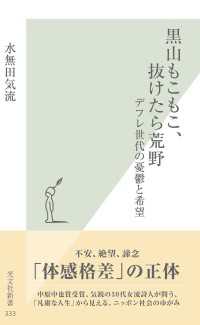- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
USJ大学生&飲食店バイトのツイッター問題、歩きスマホ&自転車スマホ、電車の列の横入り――とかく今の日本は迷惑行為だらけ。しかし、何が迷惑なのか、何が正しいのかなどというのは、実は微妙なバランスで成り立っており、ちょっと視点をずらせば、良いとか正しいという基準は、かんたんに変わってしまうのである。「迷惑学」の観点から、迷惑行為とされるものの数々を徹底的に考えてみた。
目次
プロローグ そもそも迷惑行為とは?
第1章 なぜ、夜の幹線道路は誰も制限速度を守らないのか?―「記述的規範」と「習慣」の影響力
第2章 電車内では携帯電話の電源を切るべきか?―迷惑行為と、場所・時代との関係
第3章 なぜツイッター騒動は繰り返されるのか?―ルールと迷惑の微妙な関係
第4章 どうすれば列の横入りをやめさせられるのか?―迷惑行為の抑止策
第5章 ベビーカー問題はどうしたら解決できるのか?―クリティカル・シンキングで考える「落としどころ」