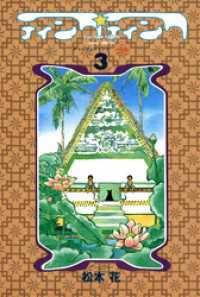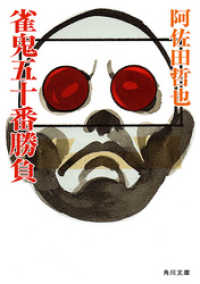内容説明
「漱石先生、その漢字、振仮名なしに読めんゾナモシ!」と嘆息したくなるくらい、明治の文豪が使った日本語が現代人は読めなくなっています。
たとえば「几帳面」と書き「ちゃんちゃん」(漱石『三四郎』)、「整然と」で「ちゃんと」(蘆花『不如帰』)、「歴々と」で「ありありと」(花袋『田舎教師』)、「深沈と」で「しんめりと」(二葉亭四迷『其面影』)といった具合。「吾輩ハ猫デアル」の言を借りれば「頓(とん)と見當(けんたう)がつかぬ」ものばかり。
国語の先生もてこずり、学校では教えない、辞書によっては載ってもいない、漢字の読み方。近代文学の原文の行間に光彩を放つ「振仮名」の魅力、その知的遺産に触れる旅、すなわち「百年前の日本」へタイムスリップするガイドブックとしても楽しめる一冊。江戸の粋と明治大正の自由奔放に〈たっぷり・どっぷり〉つかる200問にぜひチャレンジしてみてください!
目次
《味わう前の食前酒の章》明治期の漢字表記
【第一部】漱石作品の漢字表記を味わう 『吾輩ハ猫デアル』『坊っちやん』など
【第二部】鴎外作品の漢字表記を味わう 『詩人』『青年』『雁』『高瀬舟』
【第三部】近代黎明期の漢字表記を味わう 『西洋事情』『当世書生気質』など
【第四部】明治中期の漢字表記を味わう 『たけくらべ』『金色夜叉』『若菜集』など
【第五部】明治後期の漢字表記を味わう 『海潮音』『其面影』『田舎教師』など
【第六部】白秋作品の漢字表記を味わう 『邪宗門』『思ひ出』
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひめありす@灯れ松明の火
53
今は使わなくなった言葉達。形を変えた表現。どういう用例があるのか、歴史的背景があるのかなども一つずつ説明がついているので、賢くなった気分で読みました。普段読んだり書いたりで使っているものが、実は難読だった!とか気がついて吃驚しました。だって、パソコンで変換すると出てくるんだもの……さすが日本の技術力!クイズの部分はヒントがあるので、何となくわかっちゃうかも。今は助詞を漢字で書く事は少なくなりました。と言うので手元にある本を見返してみたりしました。泉鏡花の日本語もすっごく可愛いので、何時か取り上げて欲しいな2014/10/17
tomi
39
漱石、鴎外ら明治の文学作品に使用された難読漢字をクイズ形式で出題し、「言海」での用例等も参照しながら解説する。挙げられた中には現代でも普通に使われる漢字も少なくないが、作家独自としか思えない当て字の類いなど、やたらと難読。「交際(つきあい)」「財産(たから)」「市街(まち)」… 難読だけど、こういう当て字は現代の歌詞にも引き継がれてる。2018/11/16
ばりぼー
36
単なるクイズだけではなく、引用した原文を示して明治の雰囲気を伝える最大限の配慮をした資料としても貴重な本。日本語を漢字で書く書き方は「音・訓・義」の三つがあり、「義」というのはいわゆる当て字のこと。明治期には漢字の右側に「語の発音」、左側に「語義の補助的説明」という「左右両振仮名」があったのは興味深い。例えば「壓抑」の右側に「アツヨク」、左側に「オシツケル」という具合に。驀直(ましぐら)、厶います(ございます)、嘸(さぞ)、莞爾と(にこにこと)、鳥渡(ちょっと)など、ヒントがないと確かに読めません。2016/11/12
Kouro-hou
13
明治期の文豪の文章などを中心に難読な熟語を解説した本。市街と書いて「まち」と読ませるとか、手巾と書いて「ハンカチーフ」と読ませるとか。漱石、鷗外辺りは馴染みがあるので何となく読めたり、解説で納得できますが「海潮音」辺りは歯が立ちません。外来語に漢字をあてるタイプはさらに難読で「拿破崙」で「ナポレオン」とか自分には無理です!この辺は筆者の自由で「バケツ」に何故「馬尻」の字をあてたのかは本人しかわからないそうです。をを。キラキラネームとはまた違う知識に裏打ちされた漢字の魅力を教えてくれる本。2014/05/20
双海(ふたみ)
12
漱石、鷗外、諭吉、逍遥、一葉、藤村、蘆花、涙香、荷風、花袋、白秋などの原文を味わいつつ、そこに出てくる難読漢字を紹介するという本。2014/01/18