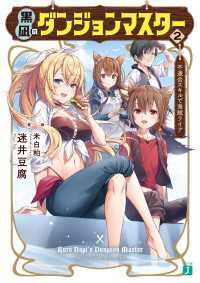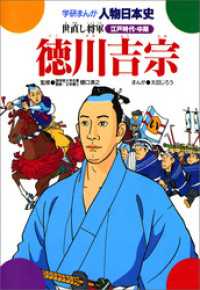内容説明
淀川、利根川、木曽川、筑後川の四大河川を中心に、日本人がいかに水と緊密に関わりながら国土と文化を築き上げてきたかを、ロマンあふれる筆致で描く。水問題、環境問題を取り上げ、社会に警鐘を鳴らした先駆的な名著として知られ、農林漁業の役割を見直し、日本人のアイデンティティを考えるための必読書でもある。姉妹編に『水の旅』がある。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
49
淀川、利根川、木曽川、筑後川…河川を巡りながら、そこで営まれている人々の文化と川の関わり合いを描いて入る。ただそこにあるのは単なる紀行文ではなく、それぞれの川の持つ問題点を近代の問題として捉えているのが特徴。それは三十年前の本にも拘わらずここで問題提起されている事柄は全く解決されておらず、むしろ深刻化してると言える。それだけこの本の内容が光っているとも言えるが。問題点は多数あるが、中心となっているのはやはり都市と地方の関わり合い。過疎とかだけではなく、水をめぐっての生存圏の争いがあるみたいに捉えれたなあ。2014/10/13
kk
13
『川は生きている』の富山和子先生の代表的著作。4つの河川とその流域の変遷を紹介しながら、「川の水はなぜなくならないのか」という問題意識の下、人と自然の関わり方に深い思いを致すもの。「緑」と「水」と「土」は基本的に同義であり、就中、人々の命と暮らしを根本的なところで支えているのは「土」であるという主張。そして、本当の意味での環境保護のためには、人々による営々とした手入れが不可欠であることを忘れてはならないとする。大切に胸に留めたい指摘です。美しく磨きぬかれた文章も素晴らしいです。多くの方にお勧めしたいです。2022/04/29
み
1
非常に面白かったし,大切なことがかかれていると感じた.最初は川を通した文化史なのかなと思っていたけれど,「文化」の重要性を現代の社会の課題や科学技術の話と絡めて描いている.自分の考えと似ていたからかもしれないけど,素晴らしかった.姉妹編も読みたい2018/04/19
aki
0
林業も扱っていたので、より興味を持って読めた。2017/08/13