- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「帰化」と「渡来」の語を明確に区分、古代史に風穴をあけた泰斗による、「渡来人と渡来文化」の集大成。近年の発掘調査の成果も踏まえ、古代国家形成にかかわる渡来を東アジアという視点でダイナミックに提示する。
※本作品は紙版の書籍から口絵または挿絵の一部が未収録となっています。あらかじめご了承ください。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
榊原 香織
82
かって”帰化人”で一世を風靡したが、呼称に問題あり、と著者自ら、渡来人、と言い換えてる。 日本海も、古代の書には北ツ海、とあるからそれで行こう、と、微妙な配慮。 後半の、道教と役小角、あたりに興味がある。”日本書紀”に、駿河の辺りに道教らしきものがあった、と出てるらし。2021/08/09
やいっち
66
数年前に読んだばかり。書店へ足を運べないので、書庫から物色しての再読を三か月以上続けている。 二週間ほど前、『日本の渡来文化 座談会』(司馬遼太郎/上田正昭/金達寿 編 中公文庫)を読んだこともあって、その流れでもある。以前も書いたが、日本と朝鮮がいかに深く関わってきたか、さらには日本という国家や文化伝統の成り立ちにいかに深く…想像以上に朝鮮からの渡来の人々が関わってきたかを再認識すべきと考えている。2020/05/26
やいっち
8
本書の「あとがき」で、筆者は、『新選姓氏録』に言及している。同書において、平安京の千百八十二の氏が、「皇別」(真人姓氏族とその他の皇別)・「神別」(天神・天孫・地祇)そして「諸蛮」(漢・百済・高麗・新羅・任那)に分けて構成されている。2016/06/25
isao_key
7
日本海について『日本書紀』垂仁天皇二年是歳の条や、『出雲国風土記』、『備後国風土記』に「北ツ海」と呼ばれていた記述がある。日本海の名称を初めて使ったのはイタリア人宣教師のマテオ・リッチで、1602年に北京で作成した「坤輿万国全図」の中に漢字で「日本海」と書き、太平洋を「小東洋」としるしたのが始まりのようだ。日本では蘭学者の山村才助が享和2年(1802)『訂正増訳采覧異言』の中で初めて使った。儒教は、渡来人によって仏教と同じく百済から伝来した。清水寺の建立を発願したのは、坂上田村麻呂だったとは意外な事実だ。2014/10/23
しょ~や
2
渡来人ってとてもたくさんいたんだなって驚いている。学校では渡来人というキーワードの他ほとんど学ばなかったような記憶しかない。2019/06/22
-
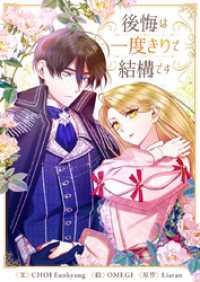
- 電子書籍
- 後悔は一度きりで結構です【タテヨミ】第…




