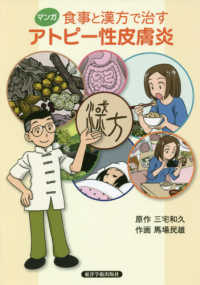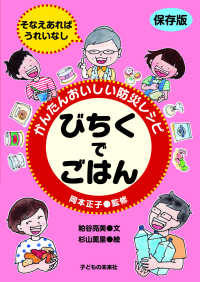- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
真面目だが消極的で反応がうすく、「どうにか無難にやり過したい」という考え方が主流。ゆとり教育を受けた、1980年代後半から2000年代前半生まれの「ゆとり世代」にはそんな傾向が見られる。若者の教育に20年以上携わってきた著者も、彼らを目の当たりにした当初は失望しかけたこともあった。しかし彼らの「自分だけ取り残されたくない」という感情をうまく使って力を引き出す「逆手指導ステップ」を編み出したことで、失望は希望に転換した。学生たちは「一週間で新書を五冊読む」などのハードな課題をしっかりこなし、驚くほど伸びたのである。本書はそのメソッドのほか、「注意するときは『肯定→アドバイス→肯定』」「本音を知りたければ紙に書かせる」「腹を割って話す必要はない」など、若者とうまくコミュニケーションをとって成長させるための「現場の知恵」を伝授する。最終章に「若者たち自身が考える、若者のトリセツ」も付す。
目次
第1章 コツを掴めば、今の若者は驚くほど伸びる<br/>第2章 若者たちは意外にがんばれる<br/>第3章 日本の組織には、「褒めコメ」が足りない<br/>第4章 若者との“異文化”コミュニケーション術<br/>第5章 タイプ別・「困った若者」の処方箋<br/>第6章 若者たち自身が考える、「若者のトリセツ」
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おしゃべりメガネ
151
私が今一番悩んでいる職場における「若者」との接し方について、色々と参考になりました。極力、偏った目でみないようにと心掛けてはいるつもりですが、やっぱりどこか偏見になってしまう時があります。何事に対しても決めつけや思いこみはいけないなと改めて感じました。特に最終章の「若者たち自身が考える『若者の取説』」は色んな意味でちょっとした衝撃でした。「ゆとり世代」と言われるがゆえの悩みや戸惑いが彼らなりにあるんだなぁと。言わないとやらない、言えばしっかりやる、自分達が育った環境とは大きく違っていることがわかりました。2017/09/12
おしゃべりメガネ
119
3年ぶりの再読です。この度、自分が管理職になったのを機に改めて読み直そうと手にとりました。前回読んだ時よりも、よりいっそうリアルな感じで読み進めていけました。自分の職場に「若者」が四人いますが、どの担当もしっかりしていて、幸いにあまり悩まされるコトはないのかなと日々感じています。『ゆとり世代』かどうかは別にして、人間誰しも'褒められる'ことで、よりいっそう頑張ろうと上を目指してくれるので、そういう部分をしっかりと意識して取り組んでいけたらなと。最後の若者たち自身が考える『若者のトリセツ』が良かったですね。2020/08/14
ehirano1
85
昨今の若手の育成における要諦は、山本五十六の「やってみせ・・・・・」なんですね、ってこれ、今も昔も変わらないということでもありますね。2015/10/08
ehirano1
63
えらくチャレンジングなタイトルです。今は「ゆとり世代」が的になっていますが、「団塊世代」、「しらけ世代」、「新人類世代」、「バブル世代」、「団塊ジュニア世代、ロスジェネ世代(当方はここ)、氷河期世代」、果ては「ゴジラ世代」なんてのもあるとか。各々の世代についても取扱書を書いていただけないものでしょうか。2016/02/10
Miyoshi Hirotaka
38
若者には時代のレッテルが貼られる。共通一次試験やインベーダーゲームの記憶を共有する私の世代は新人類と呼ばれた。私の子供らは、学習内容の簡略化の影響で、ゆとり世代と呼ばれ、最近、何事にも欲がないさとり世代が登場した。一方、若者はどの時代でも異端児。わが国が軍隊的規律で動いていたはずの時代でも「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ」という経験則があった。山本五十六の名言をシステム化したものはコーチングとして普及している。あらゆる時代において若者を動かすことは年長者にとっての難題。2019/12/19