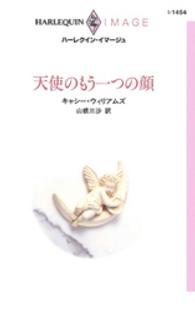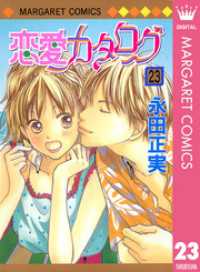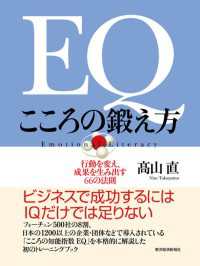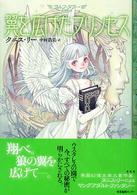内容説明
バブル崩壊以降、危機の度に生じる「円高」から日本経済の長期停滞の核心に迫ります。円高という根本原因を放置しては、財政出動も、構造改革も、何の効果も持ちません。アベノミクスのロケットスタートも、「3本の矢」という政策よりも、むしろ「円安」によってもたらされています。韓国、スウェーデン、フィンランドは、金融危機に陥った後、通貨安によってV字型回復を遂げ、輸出主導型経済に転換しました。これ以外に日本経済復活への道はありません。アベノミクスの今後を見極める上で必読の書です
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
120
この本を読んでやっと納得のいった理解が進みました。小泉政権が5年半の長期になったのは、「いざなぎ景気越え」という好況がグリーンスパンのおかげで生じたからと喝破されています。何も郵政民営化ということが原因ではなかったということです。それで安部内閣のブレーンのせ世耕しらが、かなり景気のことを言っておられるわけです。アベノミクスについても、三本の矢とはいいながらもやっていることは低金利下では効果のない金融政策ばかり、ということを分析されています。昔から竹森さんの分析には一目おいているのですが、この本を読んだ甲斐2016/05/24
isao_key
11
通貨危機が起こった際に、通常国の通貨は下落するのに、なぜ円高となるのかについて説明している。それによると「日本の民間企業は、国内で困ったことが起こると、海外に蓄えているドル資産を取り崩して、国内に持ち込もうとし、それで国内の資金繰りをつける。この場合、ドルを円に戻す必要が出てくるから、円買い、ドル売りの殺到となり、<円高>になる。さらに<思惑>が拍車を掛け、資金繰りに問題のない投資家まで、<円高>への流れを読んで、円買い投機をするので、ただの円高ではなく<超円高>になる」のだと説明している。分かりやすい。2016/07/16
スプリント
5
経済危機や災害などが発生しても円だけが急落せず、逆に円高になる仕組みについて理解ができました。2016/05/15
hijilist
3
著者の主張を一言でまとめると、「日本経済浮上のカギは、構造改革ではなく、円安による輸出拡大」。正直、説得力に欠ける上に時代に合ってない(輸出主導で回復した事例が全て90年前後)。冷戦後の経済環境の大きな変化、円高対策で「構造改革」した日本企業の実態なども踏まえると、こんな結論にはならないと感じた。現に、円安に振れても販売数が大きく増加しておらず、そんな単純な話ではないと思う。2015/12/03
TH
3
地震や危機の際にどうして円高になるのか。そんな疑問に参考になった。TPP亡国論についてこの著者もゲラゲラ笑ってしまったと書いていて、私も以前「TPPで外国から安いものが入ってきてデフレが悪化するからダメだという話は???という感じ。」とレビューを書いていたので共感したw2013/12/07