内容説明
犯罪者に反省させるな──。「そんなバカな」と思うだろう。しかし、犯罪者に即時に「反省」を求めると、彼らは「世間向けの偽善」ばかりを身に付けてしまう。犯罪者を本当に反省に導くのならば、まずは「被害者の心情を考えさせない」「反省は求めない」「加害者の視点で考えさせる」方が、実はずっと効果的なのである。「厳罰主義」の視点では欠落している「不都合な真実」を、更生の現場の豊富な実例とともに語る。
目次
第1章 それは本当に反省ですか?(2度の接触事故を起こした時の私の本音 「後悔」が先、「反省」はその後 ほか)
第2章 「反省文」は抑圧を生む危ない方法(「模範的な反省文」から読み取れること 反省は抑圧を生み、最後に爆発する ほか)
第3章 被害者の心情を考えさせると逆効果(被害者の視点を取り入れた教育 矯正教育なんかしない方がマシ? ほか)
第4章 頑張る「しつけ」が犯罪者をつくる(りっぱなしつけが生き辛さを生む 「しつけ」がいじめの一因に ほか)
第5章 我が子と自分を犯罪者にしないために(問題行動の背景をいっしょに考える 親から「迷惑をかけられたこと」を考える ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鉄之助
396
衝撃的なタイトルだけど、中身は心底からうなずけた。いかに表面的に「反省」させることが、罪なことか! 平気で反省文を書かせる親、教師、刑務所の刑務官。その行為が、将来の犯罪者を生み出している事実に、皆が気付くべきだ、と強く思う。2025/01/10
ネギっ子gen
75
刑務所における受刑者の更生を支援する現場から生まれた本。昨今の犯罪に対し厳罰化を求める声に対し、著者は言う。「私は厳罰化の方向には反対です。理由は、思い罰を与えても人は良くならないどころか、悪くなるばかりだから」と。「受刑者は、幼いときから周囲の者に何度も叱られ、反省を繰り返しています。それでも、また悪いことするのです。それがエスカレートした結果が犯罪」。だから“世間向けの偽善の反省”を求めず、支援者側のスタンスや刑務所の体制を変えることの方が、真の反省につながると説く。関係者にはぜひ読んでいただきたい。2019/11/30
こばまり
66
『ケーキの切れない〜』からの芋づる読了。確かに反省と後悔は全くの別物と感じ入る。人は誰しも、そのままの自分を丸ごと受け入れてくれ、甘えさせてくれる存在を必要とする。だから高倉健も倍賞千恵子を切望するのだ、幸福の黄色いハンカチを目指すのだ。2019/08/22
だんぶる
55
いろんなところで反省は必要になってくる。相手を納得させるための反省では根本的な解決にはならない。自分、自分達のための分析・再発防止策が大事。反省する技術ばかりが上手くなっていないか?発生した現実の原因をきちんと掘り下げる必要がある。2015/11/22
鷺@みんさー
53
なかなか直球なタイトルだが、要点は「非行は抑圧の爆発点。吐き出させるべきであって、反省を無理に押し付けると表面上で終わってしまい、犯罪者や精神疾患になる」というものだった。まあわからなくもない。支援者として多くの犯罪者と関わってきた著者の一つのリアルなのだろう。ただし、個人的に大事な人が被害にあったら、自分の主張は別として加害者を自ら罰したい、と素直な本音を最後に書いてる点は良いと思った。2020/05/09
-

- 電子書籍
- おもしろ踏切大百科
-
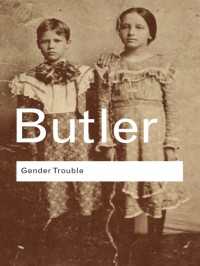
- 洋書電子書籍
- ジュディス・バトラ-『ジェンダ-・トラ…






