- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
夜行を乗り継ぎ、現場調査に明け暮れた若き日々、「見えないものを見る力」を学んだドイツ留学時代、徹底的な調査研究で、日本の森の真実を知った10年間、そして、自らの理論を基に、いのちを守るふるさとの森づくりへ。日本一木を植えている科学者の理論と実践を知る決定版。(講談社現代新書)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アナクマ
27
とことん現場に学んで確立した潜在自然植生の10倍速森づくり、宮脇方式。地道な基礎研究、人材の多様性の重要さを示す好事例。功績は大きい。◉しかし森を「造る」は序章にすぎず、その後の「つきあいかた」は依然として残る根源的な課題。世界的な資源状況を鑑み、日本の森林を再生可能なものとして見た場合には、(著者も必要性を認めている)スギ人工林も、(いのちの森など不可侵と定めた場所を除く)潜在植生人工林も、持続的に賢く利用することに知恵と決断を集めることが不可欠と考えます。◉まさしく「このあとどうしちゃおう」です。2017/12/24
Sakie
15
日本の本来の森(原植生)は現代の日本にほとんど残っておらず、あとは全て人間が改変したもの(現存植生)だという。少なくとも広葉樹林は、本物の森だと私は思っていたが、自然な森ではないと知った。著者は何十年も各地の現地植生調査を行ない、もともと生育していた土地本来の木(潜在自然植生)を突き止め、その苗を多層になるよう、また競争原理が働く形で密植することによって、「人間が管理せずとも維持できる森」を早く生育させる方式を編み出した。長期の観察から導かれる論理は強い。とりあえず神社の鎮守の森を見に行こう。それが本物。2023/12/23
ハチアカデミー
15
戦後の高度成長期の中で、公害が問題となり、自然破壊の弊害が改めて考えられるようになった時期に、企業を、国を動かして「鎮守の森」を日本各地に再現せんとした植物学者の人生語り。現在日本の森林の多くが「マツ・スギ・ヒノキ」であるが、それは人が造林された人工林であり、土地本来の森ではないと指摘する。近代化によって、工業に利用可能で、成長が早い植物が植えられたのだ。著者はそれを「ニセモノ」の森と指摘するが、近年はやりの里山はいかに… 感情の人なので、本書のすべてを鵜呑みにすることはできないが、学ぶことは多かった。2014/07/17
めんま
9
全体的にヒロイックな調子で書かれていることは気になる。ただ、その土地が潜在的に適した樹木を持つという潜在自然植生という概念はすごく面白く、今の日本では森があるように見えても、実は土地に合っていない樹木の集まりであり、脆弱なのだという観点は目から鱗だった。2021/02/18
ぼのまり
9
漠然と神社など宗教的な意味合いで考えていた「鎮守の森」だが、日本の生態に本来適合した森であるからこそ、神社などがまつられたと考えるのが正しそうだ。杉や松、檜など一見緑が多く見えるようであっても、これらは造られた森であり、その土地の持つ生命力は発揮するにいたっていない。近くの神社などの木々も見てみようと思う。神聖に感じるのは木々と土地がシンクロしているからに違いないのだ。2013/08/20
-
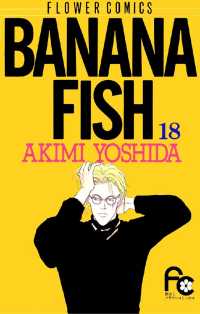
- 電子書籍
- BANANA FISH(18) フラワ…




