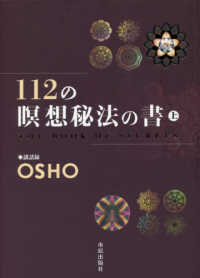内容説明
東日本大震災から、日本列島は大きく動く時期にはいっている。明日にも迫る大地震を前に、歴史を丹念に見ることで、大地の揺れがどこでくり返されるかが浮かび上がってくる。次に危惧されている首都圏、南海トラフに焦点を合わせた注目すべき書。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
もくもく
4
寒川先生の講演会を聞きに行くので、本書で予習しています。 地震考古学者と称する著者は、古文書にのこる記録、遺跡調査で得られる地震の痕跡、などから、日本列島の地震被害の歴史を次々と読み解いていきます。 この国は、どこがいつ地震に襲われても不思議はないということを、歴史的な証拠を突きつけられて再確認した思いです。2014/01/18
うーちゃん
2
読んで面白い本では決してない。むしろ、歴史上の事実と、その当時に起きた地震を機械的に羅列しているだけとも言える。それでも、読んで良かったと思った。日本全国いつどこでも、大地震が起きておかしくないということが肝に銘じられたからだ。この筆者の本を読むのは「地震の日本史」(中公新書)に次いで2冊目だが、こっちを優先的に読んだ方が良い。東日本大震災が起きたことを踏まえて、最新のデータが載っているからだ。2013/05/21
bittersweet symphony
0
コンスタントに出るようになった寒川旭さんの地震考古学本の最新刊。地震考古学はプレート境界を中心とした地震の周期性を文献と考古学発掘情報から明らかにしようというコンセプトの学問ですが、本書もその線に沿ってまとめられています。ただし時系列と地理的な順序が全体を通すとバラバラなため、全体像を把握するのには若干難儀する印象があります。本書を読むだけでは切迫感が感じられませんが首都圏直下地震は秒読み段階、何気に南海トラフ地震よりも緊急度が高いように見えるのは、十勝・根室沖と琉球海溝のプレート境界地震という印象。 2013/03/26
takao
0
液状化などから探る巨大地震の痕跡2018/10/04
-

- 洋書電子書籍
-
絵文字と大学の公衆衛生教育
Em…
-

- 電子書籍
- 紙の爆弾 2021年7月号