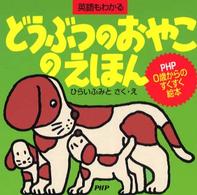- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
日露同盟か、日米提携か、集団的相互安全保障か、それとも――。第一次世界大戦以降、日英同盟が空洞化し、中国をめぐる欧米との軋轢が進むなか指導者たちが描いた外交構想とは? 山県有朋、原敬、浜口雄幸、永田鉄山という大戦間期を代表する4人の世界戦略を読み解く。現代の安全保障を考える際の手がかりとなる一冊。(講談社現代新書)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
58
日本は昔も今もアメリカと支那との関係をどうするのかによって安全保障が決まるのだなぁということを実感。本文は若干長ったらしく感じる表現が多かったが、戦前の日本の安全保障について詳しく描かれている。2013/02/05
Tomoichi
21
山県有朋、原敬、浜口雄幸そして永山鉄山の4人それぞれの安全保障政策を説明しながら、戦前の日本の外交史を解き明かす。4人のうち天寿を全うしたのは山県有朋のみ。その他3人はテロに倒れる。山県有朋の外交構想に対して批判はあるだろうが、やっぱりそれは後知恵からの批判だと思う。100%うまくいくものなんてないんだから。最近、原敬が気になっている。少し彼について読もうかな。2023/08/26
ロッキーのパパ
20
第一次大戦と第二次大戦間の日本の軍事戦略面を4人の政治家・軍人を中心に解説している。浜口雄幸というと金解禁など政策に失敗した政治家というイメージが強かったけど、しっかりした政略眼の持ち主だったことが印象付けられた。また、山縣有朋のときから陸軍は政策面では対米関係を対露と同じレベルで考えていたのは意外だった。陸軍がアメリカの実力を軽視して対米戦に突入したとは単純には言えないことに気づかされた。著者には新書レベルの本をもっと書いてもらいたいな。2013/04/17
masabi
14
【概要】山県、原、浜口、永田の安全保障構想を解説する。【感想】経済工業軍事の圧倒的大国英米に如何に対峙するかが当時も課題だった。日露連携、英米連携、独立経済圏の樹立に分かれたが、太平洋戦争を経てアメリカとの連携が核となった。当時から米国の覇権下で米国のなすがままにならないよう模索するなど現代に通ずる部分もあり、読んでいておもしろかった。特に原の東アジアでの英米の温度差につけこみ対等な地位を得るなど。 2019/09/07
CTC
13
敬愛する取引先の方に、メチエの『浜口雄幸と永田鉄山』を読めと言われ、とりあえず本書を再読。10ヶ月振りに開いたが…山県と永田に挟まれた原敬・浜口雄幸の2人の政党政治家の章は、随分とサラっと読んでいたようで、発見の多い読書に。 原は寺内内閣の前、大隈の外交(対華21カ条要求ほか)を「すべて失敗」とし、中国全土に広がる排日の機運と、各国の不信感を拭うため、「日支親善」と、米英との協調下での交易型産業国家を志向。米との非対称な国力差から来る潜在的脅威には、国際連盟を軸にした集団的安全保障を組み合わせ…。2017/07/19
-

- 電子書籍
- 異界の吸血鬼は大正乙女の純潔を願う 【…
-

- 電子書籍
- 奈落の底で生活して早三年、当時『白魔道…
-
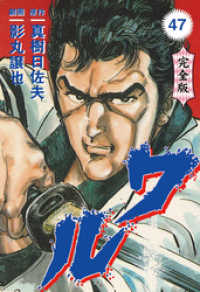
- 電子書籍
- ワル【完全版】 47 マンガの金字塔
-
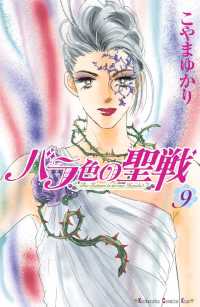
- 電子書籍
- バラ色の聖戦 The Future i…