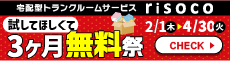- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
本書は、大学で学ぶ標準的な内容を解説したミクロ経済学の入門書。ミクロ経済学は、増税の影響や景気対策といった問題を直接は扱わないため、研究者以外の興味・関心を集めることは少ない。しかし、経済学の基本的な思考法を身につけたいなら、ミクロ経済学こそがその入り口に相応しい。大学の単位取得や資格試験のための従来の教科書とは一線を画した、「難しそうだけど気になる」「教養として学びたい」人にぴったりのテキスト。
目次
第1章 出発点から考える経済学(経済学とその思考法の思想的基礎 インセンティブから導かれる経済原理 経済学はここから始まる?)
第2章 個別主体の行動原理(個人は予算制約の中で幸せを目指す 消費者理論から需要関数へ 企業の利潤最大化行動と供給関数)
第3章 競争的な市場が望ましい理由(完全競争市場の効率性 生産経済の効率性 一般均衡から部分均衡へ)
第4章 競争条件と企業の行動(不完全競争市場はなぜ問題か 不完全競争下の企業行動 経済学における競争戦略論)
第5章 競争的な市場が望ましくない場合(公益事業のかかえる問題 外部性と公共財 情報の非対称性 経済学は再分配政策を語り得るか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
白義
13
新書サイズのコンパクトな教科書として実に巧みで、入門書の次に読む教科書としてとても適している。とりわけ、経済学への誤解を解くためにその方法論やモデルの意義の解説から丁寧にしているのが特徴的で「方法論的個人主義」という出発点からどのように市場の均衡や競争が生まれるか、そして資材が配分されるかを明かしていくスムーズな流れ。専門用語や図表、数式も出てくるものの、最小限かつ文章の流れを追うだけできちんと全体が理解できるようになっているのもいい点。姉妹編にはマクロ経済学講義も今ならあるのでセットで読むのを推奨したい2018/09/17
onaka
6
ミクロ経済学の入門書。きちんと咀嚼できないところもあったが、まずは読み通すことを重視、ザックリ、経済学の大前提となる考え方と、その目標とするところを理解した(と思う)。なんとなく遠ざけていた経済学だが、これベースに、いけそうな気がしてきた。経済学に縁のないシロウトにも優しい良書。まだ見ぬ『マクロ』の期待値も高まる。2014/02/12
おおにし
5
日経ビジネスオンラインの飯田さんのインタビューで本書をしり興味を持ちました。実際読んでみると経済学タームがよくわからない門外漢の私には難しくて最後まで読むのがやっとでしたが、「(方法論的)個人主義」「価値」「効用」などといった経済学的思考法の前提となる概念をきちんとおさえておかなければ、現代の経済学は理解できないという話だけはなんとかわかったように思います。物理学もまさに同じですね。経済学的思考法というのは身につけたいので、この教科書を時々ひもといて勉強しようかと思います。2013/02/23
Mozuku
2
方法論的個人主義や合理的主体、弾力性のような語感だけでは意味の解らない用語も解説される。功利主義と個人主義のバッティングは意識したことがなかった。 経済モデル計算は演繹的に、少ない仮定から導かれる結論は汎用性が高いとされる、らしい。需要、供給曲線はよく見るが、先に無差別曲線、費用曲線も解説される。一般均衡分析と部分均衡分析。 他社よりも1円でも安く!という少し前まで電器屋で聞いた売り文句は実のところ価格競争を回避する効果を生む、こういった手法も経済学的な思考を持てば売り手の真意を汲み取れるのは面白い。2023/02/06
とりぞう
2
電子版で読まない方が良いと思う。というのは、「数式」で表される表現を、前後のページを行き来して確認したくなるはずだから。「経済学」の「基本数式」が「中学の関数」で理解できることを知ることのできる興味深い本。でも、「中学の関数」を理解している人は少ないんだよな^^。2021/09/15