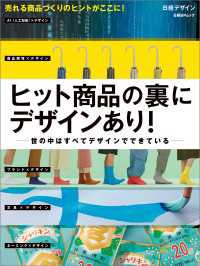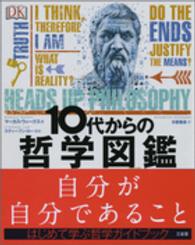内容説明
15世紀半ば、嘉吉の乱による将軍暗殺のあと、幕府は求心力を低下させ、首都近郊では一揆が続発。主を失った牢人が京にたむろし、博打に興じ、乱暴を行うなど混乱を生じさせていた。その後の10年に及ぶ応仁・文明の乱で暗闘した足軽は、いったいどこから現れ、何をしていたのか。下剋上そのものといわれた足軽の姿を明らかにし、室町時代の実像に迫る。
目次
1 首都京都の誕生(都に住んだ武家 荘園をとりまく人びと)
2 京郊荘園の変容(武家にとりいる荘民たち 広がる被官化 蒲生貞秀の成長)
3 足軽・牢人の誕生―暗転する室町の社会(足軽予備軍 没落人の行方)
4 牢人都市京都(諸国牢人上洛事件 退廃する京郊社会)
5 嘉吉の乱後の幕府政治―交錯する光と影(奉行人たちの季節 伊勢貞親登場 応仁の乱への道)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こきよ
68
政治的に不安定な土壌が、足軽或いは浪人といった法外者を生み出すに至ったのであるが、彼等が都に集まり、戦国の気風を醸成し、やがて大乱を巻き起こす流れが上下に生まれたと言ってもよかろうか。北山、東山文化といった華やかな時代でありながら、アウトローが跋扈する側面も併せ持つ。室町時代はつくづく面白い時代である。2014/11/30
mitei
48
足軽って今で言うフリーターみたいな感じに感じた。しかしこの頃の京都が歴史の中心になってたように思った。2012/12/02
niwanoagata
18
面白かった…が、読むのに時間をかけ過ぎた(まとまった時間が取れなかった)のと、自分が荘園とか擾乱以降応仁の乱以前あたりの政治情勢に疎かったせいで多少理解に苦しんだ 荘園の管理や都との繋がりなど、知らないことが多い分ハッとさせられるところも多かった。ただどこか理解しきれてないのか、読み終わってスッキリはしなかった。もしかしたら理解できてれば反論乃至何かしら言いたかったのかもしれないが、やはり理解しきれてないので自分でもわからない もう少しこの時代を勉強した後にもう一度読んでみたい。全体的に面白かったのは確か2020/04/25
Jampoo
12
室町時代の政治的、社会的状況の変動から足軽誕生の背景を探る。 税収や紛争解決など様々な局面で従来の階層的な構造が機能しなくなっていき、幕府や荘園の権力が綻び、階層も流動的になっていく様には「戦国」へと繋がる波の始まりを感じる。2025/06/17
May
7
幕府が京に拠点を置いたことに始まる室町時代論。「足軽の誕生」までの政治的、社会的経緯が主題。著者の主張(2012初版)が今(2024)どのように評価されているのか分からないが、面白く読む。「むすび」に主張が論理的にまとめられているので、まずはここを読もう。その上で本文に当たった方が理解が進むこと間違いなし。都鄙交通の活発化、牢人流人の流入、政治制度の疲弊と改革、それによる守護の台頭などなど。2024/12/01