内容説明
デビュー作『空白の五マイル チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む』で2010年第8回開高健ノンフィクション賞、2011年第42回大宅壮一ノンフィクション賞、2011年第1回梅棹忠夫・山と探検文学賞を受賞し、『雪男は向こうからやって来た』で2012年第31回新田次郎文学賞を受賞した若き冒険作家の最新作! 今なお命の瀬戸際まで人間を追いつめる酷寒の北極圏。19世紀、地図なき世界と戦い、還らなかった人々を追う、壮絶な1600キロ徒歩行! 人間の生と死をめぐる力強い物語!
目次
序章 レゾリュート湾
第1章 バロウ海峡―乱氷
第2章 ピール海峡―未知の回廊
第3章 ビクトリー岬―暗転
第4章 ワシントン湾―遭遇
第5章 グレートフィッシュ川―約束の地
第6章 不毛地帯―混沌
終章 キナパトゥの国
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆいまある
104
フランクリン隊は北極を探検中遭難。飢えで共食いしながら129人全員が死亡した。アグルーカと呼ばれるのはその生き残りなのか?この話に興味を持ったとしても、普通は冬の北極を、わざわざ全滅した難易度高いルートを辿りながら100日以上かけて徒歩で行かないよね?-40度の氷の上で橇を引き摺って、血と氷まみれになって、更に40キロの荷物を背負って、泥まみれのツンドラ。話は単調。角幡さんと荻田さん以外誰も出て来ない。二人の体力に驚く。子牛もろとも麝香牛撃ち殺して生き延びた自分を残酷だと言う場面に生の凄まじさを見る。2019/11/21
扉のこちら側
87
2016年147冊め。極地探検史上最大の謎・129人全員が行方を絶ったフランクリン探検隊の足跡を追うドキュメント。文献を追うだけではなく実際に数千キロも極寒の中を踏破して書くのはさすが角幡氏。飢餓感の中で極地の野生動物を屠殺し解体するところ、著者の体調や心理の変化にハラハラした。最近この手の話をよく読んでいるので、友人には「冒険野郎に大金貢ぎそうだね」と言われているけど、実際こんなことやりとげる人が身近にいたらうっかり資金提供してしまいそうだ。2016/03/05
ゆきち
81
探検家の著書は、1845年にヨーロッパからアジアへと続く北西航路を探し求め、カナダ北極圏で行方を絶ったフランクリン隊が見た北極を自分の足で辿る探検に出た。辿り着くまでの103日間の凄まじい様子が描かれている。北極のような極寒の地で橇を引いて歩くと、1日に5000kcalも食べなくてはならない。それでも飢餓状態になり、常に食べることだけを考え、時には麝香牛を撃ち食べたりしながら生きながらえたという。なぜ探検に出るのかと本人も思うようだ。でも本書には、行かねばわからない何かがあるのだと思わされるものがあった。2022/07/06
Tui
46
さきに著者と高野秀行との対談を読み、勢い流れで積ん読棚から引き出し読む。止められない。翌日が休みでよかった、これは徹夜本でした。過去と現在が、極北の雪原で、ツンドラで交わる。謎を追い、この先に何かあるのではと思わせる巧みなストーリーテリング(ノンフィクションですが)の虜になる。文才すごいなあ、この探検家。読み終えてから1ヶ月以上たった今でも、アグルーカの正体をめぐる謎解きの興奮と、旅の終わり近くの静かな広い湿地帯の風景を思い出し、心はさざめく。血肉となり我が身に染みついた本だ。2016/11/05
ガクガク
33
129人全員が死亡したフランクリン探検隊のルートを辿る北極圏徒歩旅行の壮絶な記録。自らの足で1600キロ、103日間を歩き通すことで、フランクリンたちが何に囚われ、何故全員が死亡するまで彷徨わなければならなかったのかという謎に迫る。つまるところ、彼らは北極圏の荒野の魅力に囚われてしまったのだ。冒険とは「圧倒的な現在という瞬間の連続の中に生きるという稀な体験」と言う著者の言にも深く肯いた。2013/07/05
-
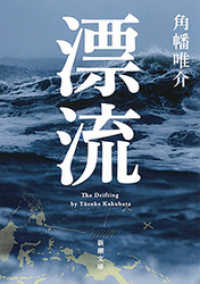
- 電子書籍
- 漂流(新潮文庫) 新潮文庫
-
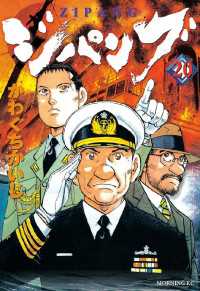
- 電子書籍
- ジパング(20)




