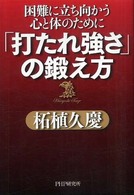内容説明
江戸時代を武士と庶民の対立の視点から、わかりやすく捉えた画期的な通史。経済の行き詰まりを倹約の徹底(デフレ政策)と庶民文化の弾圧で乗り切ろうとする幕府に、経済力と知識を身につけた庶民はどう対抗したか。忠臣蔵や四谷怪談など歌舞伎の名作の変遷や、浮世絵・読み本に現われた歓楽街の繁栄と幕府の禁令とのせめぎあいなど、江戸260年の歴史を活写する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うさを
0
江戸時代を通して盛衰を繰り返した歌舞伎という芸能の歴史をたどることで、武家政治と庶民文化が非常に複雑に影響しあった時代を描き出そうとする試みはおもしろかった。ただ、江戸時代についてダイレクトに知りたいと思って手に取ると、歌舞伎の話ばかりなので面食らうかもしれない。あと、忠臣蔵と四谷怪談の簡単な予備知識が必要かもしれない。登場人物や物語の詳しい解説がないのでちょっと混乱した。2014/12/07
なかのっこ
0
あまりVS色は強くないけど、歌舞伎の成り立ちや発展を衰退も含めて詳しく書いてある点はよかった。四谷怪談の忠臣蔵パロディをシーンごとに説明しているところが興味深かった。2014/03/28
たくのみ
0
歌舞伎の歴史から江戸時代を見るというコンセプト。「改革」のたびに弾圧され、それを逆にパワーにしてきた歌舞伎。風俗の乱れを浄瑠璃や歌舞伎のせいにして弾圧するやり方は、現代の「青少年条例」にも通じる。四谷怪談が忠臣蔵のパロディーということが詳しくわかるのも面白い。2012/11/12
サチ
0
レポートのために。2018/08/11
サチ
0
レポートの参考に。2018/08/04
-

- 洋書電子書籍
-
平和心理学とディスコース心理学
…
-
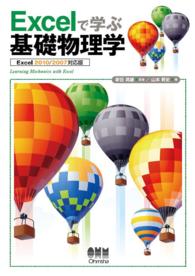
- 電子書籍
- Excelで学ぶ基礎物理学 Excel…