内容説明
『怪談牡丹燈籠』『真景累ケ淵』『鹽原多助一代記』などを自ら創作して演じ、現在でも「落語の神様」と呼ばれる三遊亭圓朝。彼は30歳で明治を迎え、近代化の中で伝統芸能を続けねばならなかった。そのために、山岡鐵舟などの政府の要人と関わって名を売り、怪談噺には「神経」という当時の流行語を使った解釈を付けて、時代の波に乗る。伝説の名人の一代記として、また、粋で退廃的な江戸から理性・倫理重視の明治へと切り替わる日本を描いた書としても貴重な一冊。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
bouhito
4
神保町戦利品シリーズ①。圓朝の作品については、現在の寄席でも多くかかっているが、実際その人となりについてはよくわかっていない。真景累ヶ淵は岩波文庫の速記本で読みましたが、この本を読むと、累ヶ淵の長い枕の意味が解き明かされる。江戸から東京へ、江戸時代から明治時代へ、江戸市民のローカル芸だった落語が、どう時代を超克していくか、そこに圓朝の苦悩があったようだ。2015/05/09
Kazuo Ebihara
1
落語家三遊亭圓朝は、前半生の30年を江戸時代に、後半生の31年を明治時代に暮らし、明治33年に没した。時代の転換期に生きた圓朝の半生を解説。山岡鉄舟らの知遇を得、谷中の全生庵で禅を学び、やがて「無舌の悟り」を得、戒名は「三遊亭圓朝無舌居士」となった。江戸から東京に変わり、落語、寄席、噺家、客層も変わり、自らの芸風を変え、怪談噺の創作は止め、人情噺や翻案噺を数多く生み出した。圓朝の速記本は人気を博し、文学の言文一致運動に繋がり、歌舞伎になった噺も多い。全生庵で毎年8月に開かれる圓朝まつり、来年は行かねば。2023/10/25
kwmr_
0
江戸末期から明治に活躍した近代文学の開祖の伝記。圓朝が作った話は今でも読んだり、聞いたりする事ができるけど、ぜひご本人の聲で聞いてみたかった。2013/06/11
yoshiyuki okada
0
落語(はなし)の昔を知る。2019/10/04
-

- 洋書電子書籍
-
ベイツ診断法(第14版)
Bat…
-
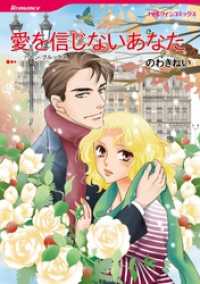
- 電子書籍
- 愛を信じないあなた【分冊】 6巻 ハー…
-
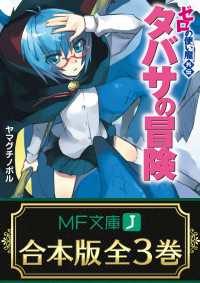
- 電子書籍
- 【合本版】ゼロの使い魔外伝 タバサの冒…
-

- 電子書籍
- イタズラなKiss(フルカラー版) 1…





