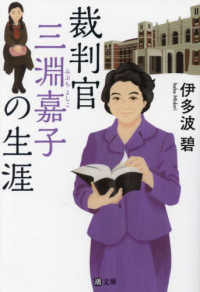- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
35
今日の日本では、精神病者が治療を中断してしまうと社会から切り離されてしまうという問題がある。本書を読んだことで、この点について深く考えてみたいと思った。2015/07/17
のの
12
タイトルだけ見ると精神疾患の治療プロセスを扱った本と思われるかも。実際は精神保健全体のことを取り上げている。日本の精神保健福祉制度を中心に、ACTやリカバリー、ピアスタッフなど話題が多岐にわたっていて、PSWの勉強をはじめたばかりの身にはよくまとまっているわかりやすい本だった。日本の社会保障はいま底辺へ底辺へ向かって突き進んでいるので、国の支援を受けてるくせにあれもこれもしたいなんてわがままだ、というような論調が増えてくるのだろうな。そうならないといいなあ。人間らしく生き合いたい、と思った。2012/10/27
アルタイル
4
精神保健や精神疾患に対する処遇や医療、福祉のあり方の変遷や、それらにおいての日本と諸外国の違いなどが分かりやすく描かれている。最初の『自分の親しい友人を三人挙げて全員おかしくなければおかしいのはあなただ』という強烈な切り口から引きつけられる。一生のうち精神疾患にかかるのは四人に一人に登る。とても身近なもので他人事ではない。日本全体にそのような認識がもっと必要なのではないか。2014/09/26
sabato
4
専門職として大切な能力である、利用者に希望を与えるということについて、アンソニー博士は「I believe in them,before they believe themselves(自分自身が信じられない彼らを、私の方が半歩前で彼らを信じる)」(6章)と述べてるそうだが、これについては、なんだかアメリカのリーダー的な、うーん、先導者的な思想が見えるな。本全体としては、精神医療の歴史や今よく取り上げられている理論や取り組みがバランス良く書かれているので読みやすい。ゼミ1向けw2012/11/15
コシヒカリ
2
私自身も軽度の精神疾患となった経験から本書を読まさせて頂いた。精神疾患がかつてどのような扱いを受け、また海外諸国と日本の対応の差を築いたのか。確定的な病名を持つことの無い心の病は、医師の裁量によって診断が別れてしまうことも考えられる。 また精神科医の単一治療ではなく、さまざまな職種の人が絡み合い当事者を当然巻き込んだ治療体制、もとい社会復帰体制を構築していくことの重要性を説いたのだろうと感じる。 本書が発刊されたのが2012年。そこから13年の歳月が経ち、世間一般に心の病は周知されたと思う。2025/05/06