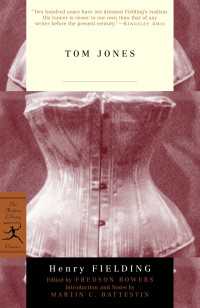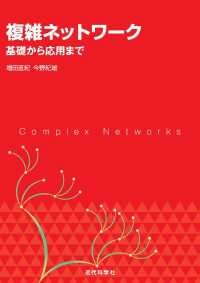内容説明
第三次近衛内閣から東条内閣まで、大日本帝国の対外軍事方針である「国策」をめぐり、陸海軍省、参謀本部、軍令部、外務省の首脳は戦争と外交という二つの選択肢の間を揺れ動いた。それぞれに都合のよい案を併記し決定を先送りして、結果的に対米英蘭戦を採択した意思決定過程をたどり、日本型政治システムの致命的欠陥を指摘する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
24
「日米開戦と情報戦』が主にインテリジェンスの側面から見たものであるのに対し。こちらは特に日本の政治過程を中心に論じたもの。副題の「非決」定」は著者も言うように「避決定」の方が意味合いが近い。つまり3年後の見通しを「不明」としたまま、開戦という「決定」を選ばざるを得なくなっていくのが恐ろしい。陸軍は多くの犠牲を払った中国から兵を引くことを嫌い、海軍はアメリカを仮想敵としていた以上、軍備確保に際しては長期戦では勝ち目がないことを承知しつつ開戦を支持する。首相になった東条がむしろ開戦に抑制的であったとは!2016/12/29
小鈴
23
昭和16年の開戦までの意思決定過程を詳細に分析しているが、ここで現れている問題はイマドキの言葉で言えばガバナンス問題なわけで、読んでしまうと16年の話だけではなんとなく物足りない。この「両論併記」と「非決定」の日本型政治システムの起源もしくは明治には効いていたガバナンスがどのように変化していったのか、その過程こそ明らかにして欲しい。政治学者や社会学者だったら思いきって詳細を捨象して理論化してくれそうなのだが、とここまで書いて思ったけどその手の本は私が知らないだけである気がしてきた。探そう。2016/09/26
鯖
19
これでよく開戦決定できたものだという呆れから始まる筆者の後書きが全て。欧州情勢の好転とアメリカの戦意喪失という希望的観測を夢見て「非決定」を重ね、目先の利益に飛びついて対米開戦という「決定」をしてしまった日本。ただ米英独伊と組織はどこも似たような歪みを抱えてるのは一緒で、結局は国力なんだろうなあって気はする。国力があるから全てを捻じ伏せ米帝は勝つ。国力負けてるんで勝てませんて現実を見据えて言える人が必要だったんだろうなあ。防衛戦争ならまだしも侵略戦争だったわけだし。2025/06/13
かんがく
18
いまさら撤兵出来ない陸軍、3年目以降の見通しがない海軍、現地と連携の取れない外務省。セクショナリズムと無責任の行き着く先が悲惨な戦争。よく、戦前日本のファシズム独裁なんて言うが、独裁ならまだもう少しマシだったのではと思う酷さ。本自体は交渉を丁寧に追っていて、各部門の反応などがわかりやすくて良い。2020/07/27
ロッキーのパパ
18
太平洋戦争直前期の政治状況を詳しく解説している。リーダーシップ不在や戦争に対する見通しの甘さが対米戦争決定の要因とこれまで漠然と感じていたけど、この本を読んでその考えがそう遠くない理解であることが分かった。後はこの本では扱っていなかったけど閉そく感の打破も大きな要因だったと思う。外交・戦争と並ぶもう一つの選択肢である臥薪嘗胆を選んでいたら、軍部だけではなく国民の閉そく感がますます大きくなったんじゃないかな。後、武藤章が絞首刑になったことへの疑問は同感。2013/10/02