内容説明
「入門書」とは、原典を理解するための補助をめざして書かれた本のことではない。ある分野やことがらを対象に、一般の読者向けに、平明な文章で書かれているというのは無論のことだが、「入門書」はその書物自体が一個の作品となっていなければならない。各分野の厳選された入門書を紹介する画期的な読書案内。
目次
第1章 言葉の居ずまい(国語辞典に「黄金」を掘りあてる―武藤康史『国語辞典の名語釈』 敬語は日本語の肝どころ―菊地康人『敬語』 奈良の都に交わされる声を探る―橋本進吉『古代国語の音韻に就いて』 人生への問いと文章の書き方―里見〓(とん)『文章の話』
切れば血とユーモアの噴き出る文章術―堺利彦『文章速達法』)
第2章 古典文芸の道しるべ(社会人に語りかける古典入門―藤井貞和『古典の読み方』 古歌を読む分析的知性の強力さ―萩原朔太郎選評『恋愛名歌集』 現代詩をめぐる「楽しい遍歴」―三好達治『詩を読む人のために』 読むことのうれしさにみちた近代小説案内―窪田空穂『現代文の鑑賞と批評』)
第3章 歴史への着地(歴史への抑えに抑えた怒り―エルンスト・H.ゴンブリッチ『若い読者のための世界史』 歴史的想像力の剣さばき―岡田英弘『世界史の誕生 モンゴルの発展と伝統』 ブルジョワの二面性を鮮明に照らす―遅塚忠躬『フランス革命―歴史における劇薬』 「記者魂」の躍如としたジャパノロジー―内藤湖南『日本文化史研究』 歴史の直接的な肌ざわり―中村稔『私の昭和史』)
第4章 思想史の組み立て(世相の向こうに「近代」の醜怪をあばく―金子光晴『絶望の精神史』 考えるべきことを考えよという指針―田川建三『キリスト教思想への招待』 思想史からの伝言―岩田靖夫『ヨーロッパ思想入門』 本の「断片」を読みふかめる―内田義彦『社会認識の歩み』 アラビア語とイスラームとの切っても切れぬ関係―井筒俊彦『イスラーム生誕』)
第5章 美術のインパルス(たっぷりとゆたかな「小著」―武者小路穣『改訂増補日本美術史』 江戸絵画の見かたをかえる異色の水先案内―辻惟雄『奇想の系譜』 画家の身にひそむ思想の筋力―菊畑茂久馬『絵かきが語る近代美術』 「名画」という価値から解放された絵の見かた―若桑みどり『イメージを読む』 二十世紀絵画に「感覚の実現」を読む―前田秀樹『絵画の二十世紀』)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あきあかね
田氏
tom
オールド・ボリシェビク
akiu
-
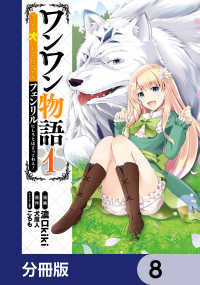
- 電子書籍
- ワンワン物語 ~金持ちの犬にしてとは言…
-

- 電子書籍
- 【ヤングチャンピオンデジグラ】林田百加…
-
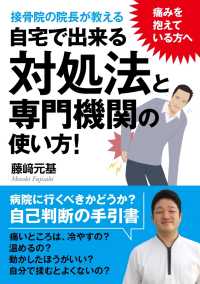
- 電子書籍
- 痛みを抱えている方へ。接骨院の院長が教…
-

- 和書
- はるかにてらせ
-
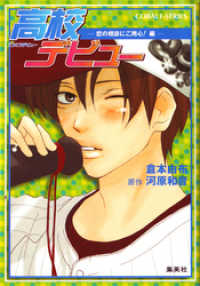
- 電子書籍
- 小説版 高校デビュー4 恋の相談にご用…




