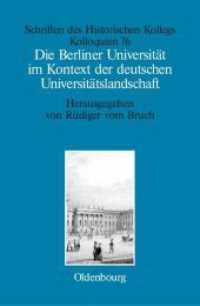内容説明
日本の中世は、地方から吸いあげた富を蕩尽し続けた時代だった。過剰なまでの消費を支えた政治・経済システムとは一体どんなものだったのか。平氏の物流戦略、鎌倉御家人の複雑極まる金融操作、悪党の経済力の本質とは? 「蕩尽」という一見非合理な消費性向に着目し、院政期から応仁の乱に至る400年の流れを見つめ直す。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
天の川
46
調べもので。「蕩尽」とは富を使い果たすことだが、内容的には消費そのものより、荘園支配をめぐる都と地方勢力や貨幣経済システム、新興勢力のパワーの蕩尽について語られる面が多かった。物流を担う輸送業者と交通網の整備が不十分であれば、地方の産物は消費されないままに朽ち果てる。貨幣経済は中世から浸透していくが、荘園領主と金融業者は経済圏を異にしており、やがて金融業者が凌駕していく。鴨長明・吉田兼好という隠遁者の清貧は、貴族社会が生み出した蕩尽の一つの型だという解釈が面白かった。過渡期の混沌さが中世なのかもしれない。2020/09/05
bapaksejahtera
17
我が国中世四百年の支配構造を蕩尽という用語で財政中心に流れを説く。荘園公領制の下、寺院の造営を中心に国土を家産として理解し、只管財貨を消費した院政は確かに書名に値するが、伝統的権威を無視した悪党のエネルギーが結局は蕩尽されて社会変革に向かうという処は牽強付会に過ぎる。但し資産はあっても財政力に乏しい権力形態が、平氏により宋銭が齎され、足利政権の財政縮小を経て中世終期に金銀採掘が盛んとなりって変化する。徴税権が債権化して謂わば貨幣化する特異な我が国中世経済が理解できた。文学や紙背文書を用いた説明も興味深い。2023/01/31
邑尾端子
7
中世社会においては資産の所有者(領主層)の経済圏と、資産の管理者(金融業者)の経済圏という二つの枠組みが別個に存在し、互いに作用しあっていた。中世初期は前者(荘園領主)に優位性があったが、時代が下るにつれて後者が前者を凌駕するようになっていく。中世史を経済構造や人々の金銭感覚という視点から読み解いていく良書。2014/07/29
mushoku2006
5
これまた分かりにくかったなあ・・・・・・。 テーマ的には非常に興味深く、 中世において、 富がどのように地方から中央に吸い上げられて、 それがどのように消費されていったのか、 そのシステム的なところが見えてくると期待したのに、 私にはさっぱり、でした。 残念 ( ̄_ ̄|||) 2014/08/21
よしあ
4
面白かった。経済を軸にした中世の移り変わり。人物メインの歴史物だと、背景になる事象が主役なので、視点が逆。人物が背景にある。 時代ごとに個々の例が挙げられている。名もない人々(と言っても、日記や文書に残った時点で名前があるのだが)の生活など、興味深い。悪人も誰も彼も、現代人のご先祖なんだよね。 現在の我々の、資本主義と言われる経済活動を、数百年先の人が振り替えって俯瞰すると、どう表現されるのだろう?と想像した。 2022/04/10