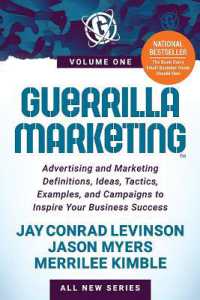内容説明
未曾有の変革期を迎えている日本の大学教育。学力低下や若者のコミュニケーション格差、そして深刻化する就職率低下――。その内実と改革の展望を、初等中等教育・大学教育の現場を踏まえ一刀両断する最新対談!
目次
序章 親が知らない大学の“今”
第1章 大学の「しあわせな時代」は終わった
第2章 高校からみた大学、大学からみた高校
第3章 大学再生のカギは現場の“教育力”
第4章 大学生のコミュニケーション力格差
第5章 大学から問う日本の未来
終章 大学は教育機関として再生する
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みしお
5
便所飯、大学におけるクラス担任制、東大の秋入学など現代の大学事情について教育評論家である尾木直樹氏と諸星裕氏が対談したもの。尾木氏の自慢話には少々辟易するが、テーマはすごく興味深くて、教育学の入門としてはすごく面白かった。特に既存の入学試験はやめ、アメリカのSATのような試験を日本に導入し、それに応じた、つまり自分の学力に応じた大学の中から大学を受験し、面接などを通して自分に合った大学を見つけるべきだという諸星氏の論には、実現できるかできないかの論はさておき、とても興味深いものだった。2012/01/03
tolucky1962
4
尾木ママこと法政大学の尾木直樹教授と桜美林大学の諸星裕教授の本です。 どちらもコメンテイターとしてTVなどでお見かけします。 一人で食事する姿を見られたくないためトイレ個室で食べる「便所飯」から始まって、大学の抱える問題が忌憚なく語られています。 耳の痛い話もあり、考えさせらます。 生き残るには企業も変化が必要なように、大学も変化が必要なんでしょう。2013/01/25
かやん
4
大学は生徒ではなく学生、教授は教師ではなく研究者と考えれば、高校までとは違う意識をもって入学するべきのだが、今はクラス単位で担任もつけて面倒見てくれないと、友達も作れないし、ご飯もトイレで食べなきゃならない…なんて幼い。尾木先生はご自身で「講義」ではなく「授業」をするので一方通行にはしない、それは教員経験からきてると。そう考えると大学の先生も教師とならなければ、成り立たないのかも。親も子も大学に何を求めるのか…高い授業料は払って終わりじゃないのだから、もう一度大学とは何をすべき場なのか考える必要がある。2013/07/16
オリバー
4
授業料を単位毎の発生は、激しく同意です、まあ言いたいことはたくさんありますが、結局のところは、何事も個人の実力次第と思います。もうあなたは大学生なのだから。2012/03/29
butuzemi3ken
4
タイトルに大学論あるが、読み進めているうちに、大学が抱えている諸問題は初等中等教育と入試の二つにあるという印象を受けた。結局、入試に振り回されてしまい小学校、中学校、高等学校では社会生活に必要な基本的能力の育成を置き去りにしまっているのではないだろうか?コミュニケーション力がその一番大きなものなのかもしれない。 対話形式で論点が解りやすく、読んでいて面白い。しかし、問題点の羅列、そして単なる下流大学批判に一部なってしまった。2012/01/27
-

- 電子書籍
- 普通の小学生が「早慶GMARCH」に合…