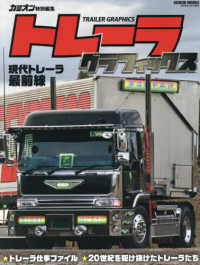内容説明
短歌をつくるための題材や言葉の選び方、知っておくべき先達の名歌などをやさしく解説。「遊びとまじめ」「事柄でなく感情を」など、テーマを読み進めるごとに歌作りの本質がわかってくる。正統派短歌入門!
目次
なにからはじめようか
遊びとまじめ
模写と風景
批評のなかでのびる
批評の基準
読むことは作ることである
初句と結句
型について
名詞をつかむ
個別化への指向
自然詠のはじまり
自然の変化に注目する
人間のいる自然詠
自然詠と自然観
社会詠のつくり方
新しい社会詠の模索
暗示としての社会詠
事柄でなく感情を
題材の選択について
比喩について
読者を予想する
結社と歌会
飛躍のための一章
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
太田青磁
48
清書するということは、自分の作品に検討を加え、批判を加える絶好の機会・大いに先進の歌をよみ、その模倣と模写を通じて、言葉を知り、歌の組み立て方を知る・自分の作った短歌を人の眼にさらした瞬間から、短歌を作ることそのものの、自分にとっての意味が、はっきり変わって行く・一助詞の置き方によって、がらりと作品の質がかわる・心の中で、一つの名詞をよびおこす・心にのこる歌を知ったなら、かならずその作者にも注意を向けるべき・歌のなかにこめられている感情を理解してもらう・性質のまったくちがうことばをもち込んでごらんなさい2015/09/24
あや
19
Kindleで読んで、これは紙の本で読まなければいけないと思い紙の本で買い直す。そもそも昔は「紙の本」という呼び方はなかったなと思う。Kindleですらすら読めた本が紙の本ではなかなか頭に入ってこない。Kindleで内容をわかった気持ちになっていたけれど、私はまだまだ短歌の入門書を読むのにこんなに時間がかかってしまうほど短歌の入口にも立てていないのだと慄然とする本。短歌についてわかりやすく書かれているけれど実は短歌とは心して詠みなさいと律されるような1冊。2021/10/05
sheemer
16
いい本だった。塚本邦雄、寺山修司とともに前衛短歌の三雄の一とのこと。叙位叙勲されている。まえがきで謙譲で実直な人間が書いたとわかる。「手を結んで」など、適切で綺麗な言葉が並んでいる。月刊「短歌」の連載からの本。石川啄木を引き短歌は「人間の感情生活の変化の厳密な報告、正直なる日記」だという考え方を著している本。表現の歴史的変遷を追い、自然詠・社会詠をわかりやすく解説ながら進んでいく。サンプルが適切で分析的アプローチもわかりやすく、深い。初心どころか入門手前にいる者にはすごくいい概説書だと思う。お薦めできる。2023/04/23
nichepale
15
百人一首は好きだが、現代短歌というものにはあまり興味がないなあと思っていたら、理由が解った。短歌には「自然詠」と「社会詠」があるそうだ/私が好きな歌は、ほとんどが自然詠であり、その中に普遍的な感情が乗せられたものであった。自分は、短歌の中で現代的なトピックや都会的な事物が語られることを期待していないことがわかった/とはいえ、何も知らない世界なのだから、まずはたくさんの短歌を読んでみたいと思う/この本はぜひ再読したい。大切なことが解りやすい言葉で散りばめられている気がするが、一読では整理しきれない印象。2023/11/12
ヨミナガラ
12
“啄木が、詩はいわゆる詩らしい詩であってはならないと言い、「人間の感情生活の変化の厳密なる報告、正直なる日記でなければならぬ」と言ったことには、わたしたちも、充分、注意すべきことかとおもわれます。(中略)「感情生活の変化」という一点に啄木の議論からの最大の贈物を見出したいとおもっています。「正直なる日記」という点についても同様です。/なにをうたうべきか、という問いかけでは困るのです。(中略)日々の感情生活の折々に変化していく、その節目、折目(中略)そこに歌の入り口がありますよ、と言いたいのです。”2014/05/13