内容説明
オーケストラにとって指揮者は不可欠のカリスマか、それとも単なる裸の王様か? どんな能力と資質が必要とされるのか? ウィーン・フィル、ベルリン・フィル、コンセルトヘボー管弦楽団を舞台に、フルトヴェングラーからカラヤン・小澤をへてゲルギエフまで――巨匠たちの仕事と人間性の秘密に迫る。
目次
序章 指揮者の四つの条件
第1章 指揮者なんて要らない?―ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団(絶美・陶酔のアンサンブル体験;ウィーン・フィルの恐るべき力量 ほか)
第2章 カラヤンという時代―ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団(凄腕揃いのチェロとコントラバス;カラヤンの残像 ほか)
第3章 オーケストラが担う一国の文化―ロイヤル・コンセルトヘボー管弦楽団・アムステルダム(伝説の奏者ヘルマン・クレッバース;ピーツ・ランバーツの回想 ほか)
終章 良い指揮者はどんな指示を出すのか?
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
手押し戦車
17
指揮者はオーケストラのそれぞれのパートを最大限に際立たせ全員が一丸となって一つの曲を奏でる。指揮者は譜面を見て解釈して楽器を演奏する人達の強みに徹底的に焦点を当てそれぞれの強みが混ざり合い最高の演奏を披露する。演奏の成果はお客さんが感動した時にこそ価値が生まれる。会社のトップは作曲し作詞してさらに、指揮者の様に事業のビジョンと言う譜面を将来に向けて解釈してそれぞれのチームを最大限の強みを発揮させることで成長させる。演奏者の強みを発揮させるためには曲に対する解釈を情熱と表現で周りを太鼓して行く事が大切2015/05/14
すのさ
6
ベルリンフィル、ウィーンフィルについての本はよく見受けられるが、今回は加えてコンセルトヘボウの章があったことでより楽しめた。常任指揮者との関係性、指揮者によって移り変わる音色等解説されている。エッセイ的な要素もあり、筆者が楽団員に直接話を聞くことができるからこその面白みがあった。これからCDを聴くのがより楽しくなる気がする。2022/02/06
またけ
5
ついつられて、フルトヴェングラーのウラニアのエロイカとブーレーズのマーラー復活をポチ2021/01/29
牧神の午後
4
最初の下野、朝比奈への短評が鋭く、そのまま一気呵成に読み進めてしまう。オケ、指揮者にまつわるエピソードが満載で、指揮者の仕事、名演の生まれる秘密、がそういうことだったのか、と鱗がおちたり、え?ちょと違うんじゃない?言っていることは判るけど、やっぱり、カラヤンのベトはイマイチだよ、とか、とにかく著者の書いていることをイチイチ反芻し、反応を返してしまうくらいに楽しい本。でも、一番の極めつけは、ヨッフムがRCOのコンマスを引き抜いたシーン。まるで、「このまま一生砂糖水を売りつづけたいか?」で、シビレタ。2013/10/09
franz
3
図書館。 ウィーンフィル、カラヤン、ロイヤルコンセルトヘボウなどについて多くのページが割かれている。 引用されていたヨッフムの言葉が良い。 “現世のことは別として、歴史的に考えてみたら、一国の存在意義は軍事力じゃない。経済力でもない。結局、文化なんですね。或る国、或る民族が人類の歴史に刻む遺産、それは文化しかない。経済的な繁栄も強大な軍事力も、時が経ってみれば単なる出来事に過ぎない。虚しいものです”2025/03/20
-

- 電子書籍
- 閉ざされた記憶【分冊】 4巻 ハーレク…
-
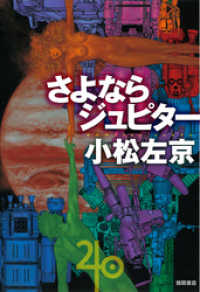
- 電子書籍
- さよならジュピター 徳間文庫
-
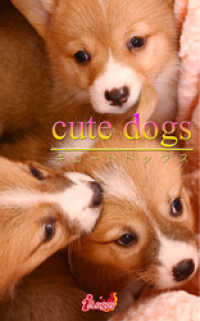
- 電子書籍
- cute dogs34 ウェルシュ・コ…
-
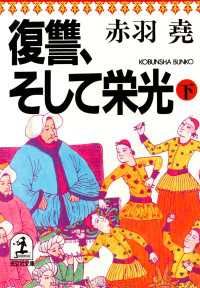
- 電子書籍
- 復讐、そして栄光 〈下〉 - 長編小説…
-
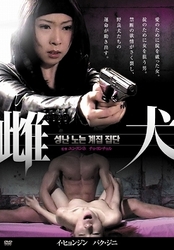
- DVD
- 雌犬




