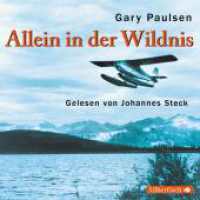内容説明
「理性」に振り回される現代世界を憂い、社会「常識」の怪しさを指摘し、虫捕りの時間がないことをぼやく。養老孟司の時評シリーズもついに完結篇。ホリエモン・村上ファンド騒動、子どもの自殺、団塊世代の定年……。さらに、幸せについて、文明についても考察。さあ、結論が見えてきた。
目次
1(定年後の団塊;抽象的人間 ほか)
2(意識は中心か;自由と不自由 ほか)
3(子どもの自殺;ぼちぼち結論か ほか)
4(結論は一つ)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かな
5
養老さんの本を読んだのはかなり久しぶり。だけど、私の大好きな内田樹さんや河合隼雄さんの本とも繋がっていて、あ~やっぱり好きな人って繋がるものなんだなっておもった。養老さんは文章が力強いな!2011/08/19
パッチ
3
養老先生の時評シリーズ完結編である。一文一文が妙に論理的で、言い切り調なのが特徴の軽快なぼやきのエッセイだ。アメリカ文明はエネルギー(石油)依存文明。アメリカの思考を知り、大人の付き合いをしようと言う。ヒトの脳は、五感から情報を取り入れ(感覚)内部で計算し(考える)運動として出力する。教育とはこの三つの訓練だが、日本もエネルギー依存だから、教育は「感覚を育てる」ことを無視し、運動せずに車に乗り、脳の入出力は単調化している。ちゃんと体を使え。エネルギーはいずれ払底する。ならば将来は人を訓練するしかないという2012/02/11
2n2n
3
文庫版あとがきを除いてすべて3.11以前に書かれたエッセイ集だが、エネルギー問題の話が一番面白かった。『エネルギーなしの生活なんて、耐えられないだろう。多くの人はそう思っている。戦前の日本人のほとんどは、日本が戦争に負けるなどと思っていなかった。それだけのことである。』の一文が、個人的には最も心にきた。2011/08/20
まつけん
2
感じたり、考えたり、というのは人それぞれ異なるものだから、お互いを理解しようとするときに言葉の力を借りるのだと思います。言葉は情報だから一応は変わらないものとして扱えますが、人は みな変わって行くのですよね。感じることや考えることを放棄して、お金や数字などの情報志向に行動するのは悲しいですね。身体を動かし五感を使って、そこで得たモノや情報をもとに考えることが大切なのだから、二宮金治郎像を座らせてしまったら大切なことが伝わらなくなってしまうな、などと取り留めのないことを考えながら読みました。2019/07/31
レコバ
2
あえて傍流に身をおくというスタンスが鼻に付くくらい徹底されていて面白い。2014/06/05