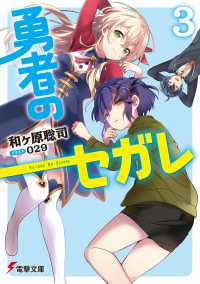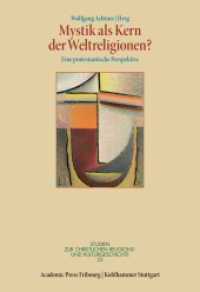- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「本当にやりたいこと」を実現するには、どうすればよいのか――? 日本仏教から失われた釈迦の教え「律」には、現代社会を幸せに生きるヒントが隠されている。理系出身の仏教学者が、古代インドの宗教界から、現代日本の科学や政治の問題まで、縦横無尽に行き来しながら、「律」に秘められた釈迦の哲学をわかりやすく読み解く。
目次
第1章 律とはなにか
第2章 「出家」という発想
第3章 律が禁じた四つの大罪
第4章 オウム真理教はなぜ壊れたか
第5章 生き甲斐の見つけ方
第6章 出家的に生きるということ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
中年サラリーマン
11
出家と律について語る本。著者が科学者出身の仏教者だからだろうか、出家という概念を科学者や政治家といったアナロジーで説明するのが面白い。また、律についても語る。例としてオウムの麻原の著書の引用を示しこれを読む限りでは多少自慢はあるが仏教的には正しいことを言っていると語る。しかし、普通の仏教とオウムを決定的に別つものは律の有無であるという。それはどういうことか?そのことを出家とは好きなことばかりできるが食っていけない、だから世間の慈悲のおかげで出家を維持できるという観点から律を語っている。2019/06/08
kenitirokikuti
5
宗教の思想や哲学は我々に「気休め」を与えてくれる。しかし、創唱宗教は必然的に結社の形を取るため、どのような組織運営がなされているのかを問わねばならない。仏教の出家集団は、釈迦から2500年も続いているため、その「律」に学ぶべきものがある、という著者は主張する▲宗教の研究と言われたらまず教義の研究が思い浮かぶが修行を目的とする結社という相はなかなか思い浮かばなかった▲「出家」についてはまた別の著作でくわしく論じているようだ。2018/02/03
in medio tutissimus ibis.
2
オウム真理教が教理だけ見れば既存の仏教との違いがないのに方や設立から十年で暴走の限りを尽くし、方や2500年の歴史を持つ世界宗教として定着できたのは、その組織運用のメソッド=律の違いによるものである。律は古代インドにおいて出家集団=サンガを修行に専心できる場にするためにブッダが作り上げた巧妙なルールであり、三宝の一つである。その中では乞食の形で社会からの支援を受けるために必要なコンプライアンスの重視、支配関係を拒む二重の序列、還俗の自由などがサンガの暴走を防ぐ。政治家や科学者もまた出家という点で参考になる2017/11/27
マサトク
2
日本に移入されなかった「律」(サンガで出家者が守るべき法)が、本来どのようなものであったのか、どのような効用があったのか。仏教教団とオウム真理教をその発生時期から比較しつつ、「律」の意味を読み解く本。要は「属人的ではない規律がないと、指導者の暴走を止められない」というオウムの例は、釈尊時代の「律」がかれによって変えられえなかったとは思わないので適切とは思いがたい部分もあるが、「律」を守っていたならこうはならなかったという例としてはわかりやすい。単純に「律」がどういうものだったかはもう少し読みたかった。 2014/04/14
くま
2
そもそもの仏教の組織っていうのは本当の合理的で、今のボランティア組織なんかにはすごく参考になるものがある。組織を維持していくためにはどうしたらいいか、っていうことに対して合理性を追求した律っていうものがあって、ぞれがあるから2500年も続いた仏教がある。今の日本の仏教に魅力を感じないのは、律がないからだとは作者は言ってないけど、そうなのかなと思う。人を苦悩から救うものが仏教だとしたら、今の仏教はそこからは程遠いように思う。仏教というのが本来何なのか、本来何のためにあるのか、教えてもらった一冊です。2012/12/15
-
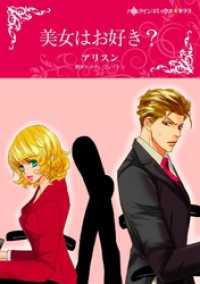
- 電子書籍
- 美女はお好き?【分冊】 5巻 ハーレク…
-
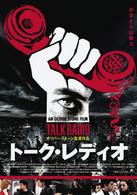
- DVD
- トーク・レディオ