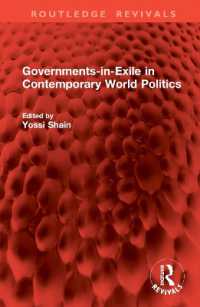内容説明
青年時代に大逆事件で叔父を失い、不敬罪で公判中に終戦の日を迎える――紀州生まれの文化学院創設者、西村伊作は、類まれなセンスと豊富な財力を理想の実現のために用いながら、「ああ言えば、こう言う」のつむじ曲がりな精神と、そのしなやかな思想を生涯貫いた。自由と芸術を愛した知られざる人物像を甦らせる第一級の評伝。
目次
第1章 最初の記憶
第2章 遠くの地震
第3章 王の法のもとで
第4章 時代は変わる
第5章 ちいさくて、いいもの
第6章 文化学院の教師たち
第7章 性の明るみ
第8章 狂気か、正気か
第9章 悔いなき生活
最終章 火を焚く夜
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たま
39
文化学院が戦時下閉鎖される逸話が『らんたん』にあり、その流れで読んだ。西村は大逆事件で死刑となった大石誠ノ助の甥。濃尾地震で両親を失い、また親しい伯父を失ったことが人となりに影響を与えたことは疑いえないが、黒川さんの描写するその言動は何とも奇矯で共感しにくい。住宅や学校などの事業には欧米社会改良思想の影響があろうが、体系的な受容ではなく、へそ曲がりの感性がキャッチしたもの。へそ曲がりが戦前の国家主義、事大主義とぶつかることで〈ちいさくて、良いもの〉、住み心地の良い家、男女共学の学校を創り出したようだ。2022/02/05
浅香山三郎
12
充実した評伝。山口昌男さんの岩波現代文庫になつてゐる一連の労作に匹敵するやうな大作である。西村伊作といふ名前は、文化学院の創始者だといふ位しか知らず、与謝野夫妻・大石誠之助との縁も断片的にしか知らなかつた。文化学院に至る迄に、建築家や生活文化の改良家、様々な事業経営と、多彩な活躍をしてゐたことは初めて知る。新宮といふ場所、キリスト教徒にはならないがキリスト教に影響された生活思想、資産家として役に立つものを見極めて使ふといふ合理主義、不思議な要素が同居して西村伊作といふ人を形成してゐることが分かる。2016/11/29
ハチアカデミー
6
西村伊作の生涯を追った人物評伝。とにかく著名な関係人物が多く、伊作を通して見た明治・大正・昭和史ともいえる一冊。叔父である大石誠之助と大逆事件までを取り上げた第1章~第4章は、新宮から見た、身内から見た大逆事件とも読むことができ、通常とは異なる角度から事件を見ることができる。一方、後半は伊作が創設した文化学院をめぐる話。各分野の著名人を講師にすえ、自ら授業のカリキュラム作成や学園の建物建築などにも関わった文化学院は彼の「理想」を実践する場であった。ワンマン故の失敗も多いが、その変遷を生き生きと描いている。2015/07/23
勝浩1958
2
両親を若くして地震により失い、熊野の地の莫大な山林を相続により受け継ぐ。また大逆事件に係わったとして処刑された大石誠之助を叔父に持ち、青年期少なからず彼から影響を受ける。 伊作は「この世に正義などはない、と思っているのではない。むしろ、「正義」への陶酔が、じきに自己欺瞞に結びつくこと」を敏感に感じていた。 だから先祖から受け継いだ財産の使い方を考え続け、『文化学院』創設へと進むのである。 また伊作本人、そして兄弟や子供たちの多くは留学を経験し、時代を先取りする人達でもあった。2011/09/18
おーね
2
あまり近代史は得意ではない私でも知っている有名人がたくさんでてくるのに西村伊作という人は全く知りませんでした。人物伝を読んでいるといつも思うのですが、人生の小さな選択が大きな方向転換になっていることにちょっと怖いものを覚えます。しかし結構女好きの人ですねえ。晩年の話ででてきますが。ただ、金持ちだという責任を自覚していたところは立派だと思いました。2011/06/26