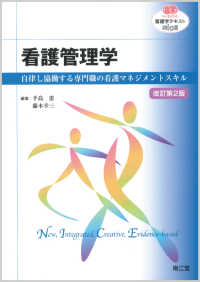- ホーム
- > 電子書籍
- > 趣味・生活(スポーツ/アウトドア)
内容説明
「一月六日 フーセツ 全身硬ッテ力ナシ…」。凍える指先で綴られた手帳の文字は、行動記録から、やがて静かに死を待つ者の遺書へと変わってゆく。迫り来る自らの死を冷静に見つめた最後の文章は、読む者の心をつかんで離さぬことだろう。この壮絶な遺書のみがクローズアップされがちな同書だが、本書では山岳史研究家の遠藤甲太氏が解説を加え、人間・松濤明の素顔と、氏の登攀史上の業績を明らかにする。松濤明の残した記録の数々を、新しい視点で読み直すための絶好の書、待望の文庫化!
目次
一九三八年(昭和十三年)
一九三九年(昭和十四年)
一九四〇年(昭和十五年)
一九四一年(昭和十六年)
一九四二年(昭和十七年)
一九四三年(昭和十八年)
一九四四~一九四六年(昭和十九~二十一年)
一九四七年(昭和二十二年)
一九四八年(昭和二十三年)
風雪のビヴァーク―一九四八~一九四九年(昭和二十三~二十四年)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
扉のこちら側
103
2016年700冊め。1948年に北鎌尾根で遭難死した松涛明の記録。前半は様々な山での行動記録の側面が強く、第二次大戦の足音が聞こえる中でも、一人の少年が自分の目標を定めて突き進んでいく姿が手記を中心に浮かび上がってくる。死が避けられないものと覚悟した時の、遺書は凄絶。2016/09/06
やまはるか
16
「死ヲ決シタノガ6.00 今14.00中々死ネナイ 漸ク腰迄硬直ガキタ」1948年12月、槍・北鎌尾根で遭難した松濤明の死の直前の手記。山をはじめた10代の頃に当時出版されていた本で読んでいた。覚悟ではないが年中山に入れば無縁ではない。山は生き延びて来たが、後から時間が迫って来た。死は感動すべきものではないが、この手記を読むと従容として向かうべきことを知る。松濤が錫杖岳登山で泊まった飛騨の宿に勤めていた女性が、この時、下山してくる松濤を上高地で待っていたことは初めて知った。手記に彼女の名は上がっていない。2021/09/08
ビブリッサ
11
1949年に北鎌尾根で遭難死した松涛明の遺稿集。記録は文章に無駄がなく、いかにも山ヤ。何時に何処に行き何分かかってソコに着いた。天気はコウコウで、こんな装備をしていた。こんな文章が多い。行動記録だからね。アラインゲンガーとしての行動が多かった松涛が、パートナーと登った時に遭難。彼一人だったら切り抜けられたろうか?そんなifは無意味だ。彼はパートナーと共にあることを選ぶ。低体温で死に向かう中、淡々と身体の状況と達観したような死生観を記す彼の精神は、紛れもなく山に向かうことで研ぎ澄まされていったものだろう。2016/04/15
ちえこ
10
雪山はほぼしないが登山はしていてこの本が気になり読んでみた、山用語が現在と違うのか、所々わからなくて調べながら読んだ、現在の道具や服でも雪山は大変なのに、私からしたら無謀としか思えないのに何にそんなに引き付けられていたのだろう?と思った。2025/04/10
リュウジ
10
★3捨てたつもりの山に戻った歓びからなのか。松濤氏の文章が俄然面白くなったのは復員した戦後から。雪を掻き壁を登る。山への憧憬と雲の描写。八ヶ岳のなじみのない南側はピンとこなかったが、土地勘のある北アの手記は彼の文学的な表現とともに味わい深く読めた。特にp188「ここは俺一人の世界」。それはソロでしか感じることができない至福(メジャーな夏山でも自分も時に1~2時間誰にも会わない時がある。あれは極上の時間)。そんな彼が死の絶望を前に凍り付きながらも遺書に残した言葉の裏にあるのは、生に対する達観か未練か後悔か。2024/11/16
-
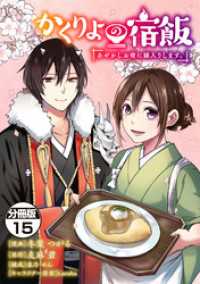
- 電子書籍
- かくりよの宿飯 あやかしお宿に嫁入りし…
-
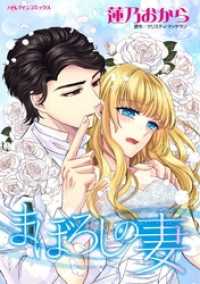
- 電子書籍
- まぼろしの妻【7分冊】 6巻 ハーレク…
-
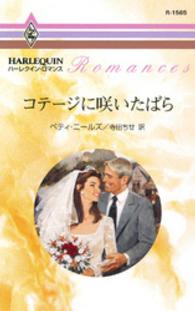
- 電子書籍
- コテージに咲いたばら ハーレクイン・ロ…
-
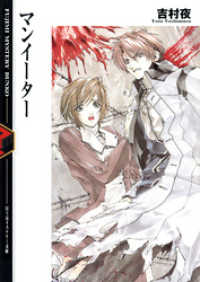
- 電子書籍
- マンイーター 富士見ファンタジア文庫