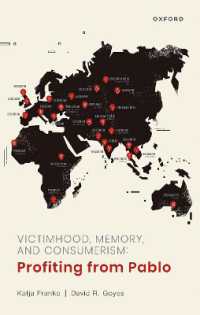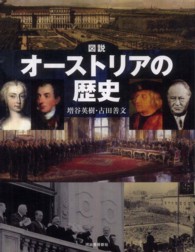- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
zirou1984
33
「風立ちぬ、いざ生きめやも」により詩人として再注目を浴びているだろうヴァレリーだが、彼の主意はその言葉に対する洞察力やそれを操る能力、即ち知性にある。WW1後に執筆または講演された内容を集めたこの評論集で、ヴァレリーはこれまでヨーロッパこそ世界そのものであったが今は世界の一部となってしまった事実を指摘しながら、人間らしさが損なわれてしまう隘路に、内面が摩耗させゆく時代に対する警鐘を鳴らしている。その言葉の切っ先は丹念に研がれたナイフの様に鋭く私の中へ切り込んで行き、何度も声を上げて叫びそうになる程。必読。2013/08/29
kthyk
16
知性の危機ではないか、世界は白痴化したのではないか、文化に厭いたのではないか・・・自由業が病んで、・・・力が萎えて、仲間も減り、その威信も次第に弱まって、がんばっても報われず、存在感が希薄になり、先が見えてきた・・・・と。こんな疑問を不意にぶつけられ、そんなこと思ってもみなかったというのであれば、考え直して、心の中でそれらの問いを反芻し、他の思念に煩わされないようにして、精神の目をこらす必要がある。精神の目とは、すなわち言葉である。「自由業の危機はあるか?」という問いへの、この書でのヴァレリーの回答。2020/12/17
しゅん
16
再読。ヴァレリーの著作から「精神」に関する文章を収録したコレクション。「精神」とは反自然的な、今この瞬間ではない過去や未来を含める(人間独自としか思えない)時間感覚から生まれる人工的な力で、ローマ、キリスト教、ギリシアが地中海で混ぜ合わさったヨーロッパ地方は異常な「精神」の発達を見せ、支配的で特異な地域となった、という論の流れ。あまりに歴史を整理しすぎな気はするが、歴史実証より理論的な思考回路から生まれた結論なのだろう。おそらく。和辻哲郎『風土』を思わせるところがある。2020/04/20
猫丸
14
「テスト氏」にも感じたことだが、この人の根柢には精神の貴族主義がある。それは世俗的な意味での出自、門閥とは無関係であるがゆえに共感できるものだ。精神的仮想敵としてドイツ的効率主義を対置するのは性急な気もするがp.136「精神は群れ集うことを嫌悪し、党派を好まない」p.252「自由の要求や自由の観念は不如意や束縛を感じない人には生まれない」などに、僕らと同じ息吹を感じる。ただしフランス至上主義者であるのは確かであり、このへんは割り引いて見なければならない。2019/01/15
いとう・しんご
12
読友さんきっかけ。19世紀末からヴィシー政権下までのエッセイ集。疎外、物象化、大衆社会、西欧の没落など発表当時でも、まして現代においては特に目新しさのない議論を展開している。内容的には新鮮味のない議論を巧みに、魅力的に展開する筆力が魅力の核心、という印象。この人は自らも言うように学者ではなく、あくまでも詩人、芸術家だったのであり、世が世なら王侯貴族の宮廷で、また、当時なら文壇やサロンで身過ぎ世過ぎをしていく人だったんだなぁ、と思いました。2025/07/23
-

- 和書
- St.ルーピーズ