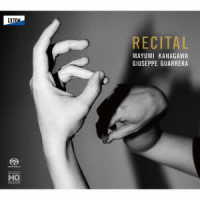内容説明
骨は情報の宝庫である。古病理学は古人骨を研究対象とし、現代の医学で診断し、その個体の病気の経過と症状を明らかにする。骨にあらわれたヒト化の道のり、縄文人の戦闘傷痕と障害者介護、弥生時代以降の結核流行、江戸時代に猖獗をきわめた梅毒と殿様のガン……。発掘された人骨を丹念に調べあげ、過去の社会構造と各時代の与件とを明らかにする。(講談社学術文庫)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
姉勤
40
出土した人骨から、当時の日本人の暮らしを探る。化石人類から江戸期まで。狩猟による怪我、栄養失調による短命が目立つ縄文時代、稲作による寿命の伸び、富の争奪による戦死が増える弥生/古墳時代。癩病、梅毒、癌…医学が未発達ゆえに、骨に深く残った傷跡。抉れ、歪んだ”しゃれこうべ”に痛ましさを感じつつ、こうなっても生きたいという人の業も。長寿になればなるほど、癒す方法が生まれれば生まれるほど、病が増える因果な乗り物。ひとは病のつまった袋とはよくいったもの。2017/06/10
どんぐり
34
古病理学は古人骨を研究対象とし、骨の情報からがん、結核、梅毒、刀傷などその個体の状態を明らかにする学問分野である。この本には江戸時代の江戸市中に埋葬された成人の頭蓋926個のうち、50個の頭蓋に梅毒と判定される所見があり、当時江戸では梅毒が広く流行していたという記述がある。骨が語る日本の社会構造と時代考証、なかなか興味深い。2014/04/30
天の川
27
調べ物で。古い人骨を研究する古病理学。発掘された人骨を調べ、社会の様相を読み解いていく。縄文人の平均余命は約15歳。江戸時代が約40歳。ほんの一握りの人々だけが、老いを迎えることができたという。時代を人骨の病変や傷から読み解いていく本書は、データが実に豊富で実証的で興味深い。縄文人の男性の骨折割合が高いことから狩猟生活の過酷さが、鎌倉時代の頭蓋の刀創から日本刀の切れ味が、病変した骨から結核や梅毒の日本への侵入時期が判明していく。先人の死を知ることで、現代人の老化や死を改めて見直す提言をされている。2014/09/18
N島
10
骨から語られる人類の歴史は、徹底してリアルでドライ。 ロマンが介在する余地は少ないが、地に足の着いた想像力が切り開く人類史に、面白みを感じずにはいられません。2014/02/11
葉っぱかさかさ
8
古病理学という研究分野があるんですね、というところから入りまして、発掘された骨から時代や生活、病気など様々なことが分かってくるという事でした。縄文人の平均寿命15歳に驚いたり納得したり、病気の流行に呪われたように死んでいく人々の姿に恐怖したり致しました。こんなに寿命が長くなった今、少子化は自然の理にかなっているのではないかと思ったり、一人の人間の生き死の儚さにぼーっとしたり、思いのほか私の感情に訴えてきたように思います。骨がいっぱい♪2017/08/18