- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
“不祥事”のあと、 何を学び、どうするかが問題だ!雑司ヶ谷下水道事故、イージス防衛秘密流出事件、三井物産DPFデータ改竄事件、シンドラーエレベーター死亡事故、加ト吉循環取引事件など、9件の事例を取り上げ、なぜ、重大な不祥事や事故が起きたのかを独特の視点で、徹底的に分析し、解決の糸口を明かす、組織人必読の1冊!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Humbaba
6
リスクはそれが実際に問題にならない限り,リスクでしか無い.そのため,それを回避するために払われるコストは小さい.実際に問題が起これば,それを解決するために多額の資産が使われる.リスクの軽減とコストの増加はトレードオフの関係にある.それを上手く調整するためには,何が問題でリスクが顕在化したのかを知る必要がある.2010/10/05
miohaha
2
樋口氏の著作3冊目読了です。不祥事や失敗から学ぶには、直接的・表層的な原因だけでなく、組織的・構造的な問題に着目する必要がある。真相がはっきりする前に誤った報道で世間をミスリードするメディアの怖さをシンドラー製のエレベーター事故のケースで改めて感じました。章の終わり方もシリーズもののホラー映画のラストシーンのようで(笑) S社ってどこ? 何より衝撃的なのはどれも当事者が私腹を肥やそうとか、悪意を持って起こした不祥事ではないということ。むしろ会社のためにという思いが裏目にでたものが多く、身につまされます。2013/04/23
Humbaba
2
人間はミスを犯す生き物である.また,システムも,人間の創ったものである以上ミスは避けられない.ミスが起こった時に,そのリカバリーをすることはもちろんだが,その上で何故起こってしまったのか,どこに問題があったのかを検証することが大切である.ミスを起こるものと考えて,その上で多重系の安全を作る.そのためにはコストがかかるが,安全はお金がかかるということを理解する必要がある.2012/03/31
たこ焼き
1
情報共有によるメリットよりも漏洩によるダメージが大きい情報の保全に関しては、官僚的な形式主義こそが正解(裁量的になると大問題を起こし得るため官僚的、形式的な態度が必要になるケースはままある。)成果とは何かをどのように定義するかによって、従業員の態度が社会および会社にとって+なものになるかが変わる。今回は緊急だから、といって会計をいじればずっとその誘惑に引きずられることになる会計のバランスシートをきれいにするために様々な架空の工夫がある。一つは循環取引。一度不正にはまって、それがばれずに済むと、味を占めて麻2016/07/25
すべから
1
色々な事例があり、勉強になった。後半の戦争の話はあんまり関係ないように思える。 『法令の理解不足や無知によって知らず知らずに法令違反を犯してしまうことが増える』『リスク対策については有無をいわさずにその方向に持っていく徹底性が求められる』『重大な失敗事案について、個人のミスだけを問題視している文献を当てにしてはならない』2014/10/10
-
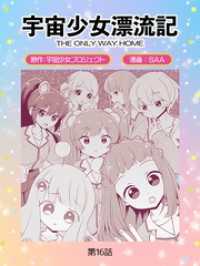
- 電子書籍
- 宇宙少女漂流記 THE ONLY WA…
-
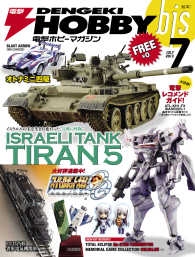
- 電子書籍
- 電撃ホビーマガジンbis 2013年7…




